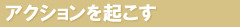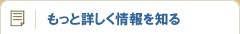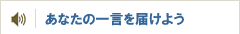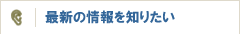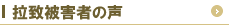有識者の声
国境なき人権報告書
棄教を目的とした拉致と拘束
第二章:現地調査の報告
イアン・リーダー教授、マンチェスター大学(英国)
日本の長い歴史の中で、複数の宗教が伝統を形成してきた。
それらは今も基盤を築いており、各宗教間では葛藤や闘いよりも相乗効果が強く作用してきた。
宗教への帰属性も、他の文化状況では一般に「あれか、これか?」の排他的選択を迫られやすいが、日本では複数の宗教的伝統に関わることが自然に行われ、環境や事情に即してさまざまな宗教儀式や行事に参加することが慣行になってきた。
最も普及してきた宗教的伝統は神道と仏教の二つの流れで、仏教が6世紀に渡来して以降、これら二つの宗教が社会文化の歴史や慣習・制度に組み込まれ、主要な役割を果たしてきた。
この二つの伝統を通して大半の日本人は宗教に関わり、社会に対する帰属意識を保持し、人生の節目、例えば子供の誕生や葬儀などに関する行事を営んできた。
神道や仏教以外で日本の伝統を形成したものには儒教がある。
儒教は日本では独立した宗教にならなかったが、東アジアで仏教が発展する過程で大きな影響を及ぼした。
また19世紀初期に近代化を始めた日本では、さまざまな新宗教が発達した。
新宗教とは日本で発生した多くの宗教運動を指すが、大半は神道や仏教や民間伝承から派生し、カリスマ的な教祖によって率いられてきた。
新宗教は当初、社会的な帰属意識とは関係なく個々人の宗教的回心で始まり、19世紀初めから20世紀後半までに数度のうねりがあった。
それぞれの新宗教が成熟して第二世代以降の信徒の数が増えるに伴い、それらの運動も信徒確保のために、改宗よりも社会的帰属意識に依存し、保守的傾向が強くなり、社会規範に忠実であることを求める傾向が強まった。
全般的に新宗教は日本の、より広い宗教的秩序に適合する傾向があり、神道や仏教が有する社会・文化的な地歩を脅かさず、また神道や仏教と関連した習俗への参加を拒まなかった。
ところが、数ある新宗教の中から社会・文化的現状に挑むことをいとわない例外的存在も出てきて、後述するような深刻な問題や葛藤をもたらした。
キリスト教も一定の存在感を維持してきた宗教である。
初めは外国人宣教師によって布教され、特に19世紀半ばに日本が開国してから広まったが、教勢は多くて人口の1パーセント程度にとどまった。
また近年、海外から流入した宗教運動で注目されるのは、エホバの証人、末日聖徒イエス・キリスト教会(通称・モルモン教)と統一教会だ。
これらの教団は今も日本での布教活動を継続している。
社会的文脈と個人の権利
普通の日本人は「家」を社会的帰属意識やアイデンティティーの核心と感じている。
そのためか宗教との関わり方も、社会的な文脈による場合が多い。
(「家」という日本語は通常「拡大家族」を指すが、日本では生存している家族のみならず、祖先として祭られる死者および将来の世代も含む。
従って、彼らのためにも宗教的伝統が持続されるべきだと考えられている。)
近代以前には、人々は主に何らかの社会的単位の構成員と見なされた。
「家」や地域社会の一員である以上、宗教上の帰属や義務も社会的単位を通して表現された。
先祖の法事や神社の祭りに参加することは、地域住民として当然のことと考えられた。
とは言っても、個人として独自の信仰や特定の宗教行為ができないわけではなく、実際に人々が望めば、一族や地元の行事などの伝統的な義務を補う形で、特定の神を拝するとか、仏教の座禅や念仏に没頭するとか、あるいは由緒ある神社へ参詣したりお寺参りをしたりといったことを自由にできる環境はあった。
ただ既述のように、人々は社会的な帰属意識と調和しながら、慣習的に認められる行為と共存する形で行うのだった。
いつでも個人が望む信仰行為に没頭できたが、それは社会の帰属や義務に適合する形で行うべきだという暗黙の了解があったのだ。
しかし戦後、都市化の進展や社会構造の変化などの影響で個人主義が強まり、集団としてのアイデンティティーが弱まってきた。
核家族化が進み、非婚の男女が増えて、従来は当たり前だった伝統行事への社会・文化的な拘束力が弱まってきた。
もう一つ、1946年に新憲法が公布され、礼拝や信教の自由が保障されたことの影響が大きい。
法律上は個人としての権利が重視されるようになり、男女とも成人(20歳)に達すれば本人の望む宗教活動に参加する自由、またはしない自由が認められるようになった。
個人が成人年齢に達すれば、法律の上では、社会や家族の圧力や指示に従う必要がなくなったわけだ。
このように個人の自律性を強調した結果、既成宗教や一族が守ってきた習俗行事や儀式との間に緊張が生まれてきた。
特に近年顕著になっている問題は、個人が信教の自由や選択権を行使した結果、日本の社会や家族構造に組み込まれてきた文化の慣習やしきたりを拒否するケースだ。
そうした問題を一層複雑にしたのは、1995年にオウム真理教が東京の地下鉄構内で起こしたテロ事件である。
それ以後、組織的な宗教について非常に強いマイナス・イメージが広まってしまった。
オウム真理教は既存の慣習や社会規範をはっきりと拒否し、入信者に家族との絆を断つよう勧め、その挙げ句に地下鉄テロを引き起こした。
このため多くの日本人は、社会のしきたりを尊重しない宗教団体を疎んじるようになった。
特にオウム真理教のように、家族や社会の規範を拒否したり、その教義と指導者に徹底した忠誠を要求したりするような信仰は危険だと見なすようになった。
そうした懸念の高まりで、世論調査が再三示唆しているように、伝統や慣習に反する教団から社会を守り、可能なら入信者を救出すべきだ、という要求が幅広く受け入れられるようになってきた。
既述のように、神道と仏教は日本の宗教的伝統の柱だった。
「神道」というのは「神々の道」を意味し、もともとは民間風俗や伝承・信仰から発達した形のない信心だったが、仏教伝来に伴って具体的な名称と体裁を有するようになった。
神道は日本とその住人を中心とした信仰である。
その中心は「神」であり、それは諸力を持つ「神々」または霊力の総称だ。
それには全国的に崇拝される有力な神から、特定の地方でのみ信心される神まで多様な顔ぶれがある。
神道の伝承によれば、日本列島では無数の神々が生命の源となり、そこに住む人々の営みを支えてくれている。
神道は日本とその住民を対象にしているという意味で民族固有の信仰であり、神話によれば日本の国土と人々は、神々の命を与える力に由来する。
そして神が皇室の祖先であり、神道は天皇家と国家と国民を一本に結ぶ極めて民族性の濃いものだ。
しかし普通の日本人にとって、神道は主として地元の習俗である。
神々は地域社会の守護神であり、地元の神社は住民の宗教行事の主要舞台だ。
人々は人生の大切な節目に神社に詣で、神々に助けを請う。
受験生が合格祈願したり、恋愛する男女が結婚の成就を願ったり、子供を授かった親が新生児を伴って神社参拝したりといった形で、神の保護や祝福を求めるのだ。
または国民的祭事を営むために神社に参集する。
中でも新年にはたいていの日本人が神社にお参りして、その1年のご加護を神に願う。
この初詣には人口のほぼ3分の2にあたる国民が年初3日間に家族や友人たちと一緒に参拝し、この時ばかりは伝統的な和服を着る女性も多い。
初詣は社会全般の喜びや国の祝い事として強いインパクトを持っている。
一方、インドで始まり、約千年後に日本に伝来した仏教は、中国と朝鮮半島を通過する間にさまざまな影響を受けた。
中でも儒教に特有な死者への祭儀や先祖崇拝、「家」を単位とする行動様式が仏教に深い影響を与えた。
仏教は日本でも重要な思想を生み、この世の人生を改善する信仰のあり方を広めるとともに模範的な精神的指導者を輩出し、救いや魂の成長に関する道徳や実践方法を生み出した。
しかし大方の日本人にとって仏教で一番関心があるのは、人が他界した時に何が起きるかを教え、死者の追善供養の法事について指導してくれるところだ。
そうした法事は家族や一族を単位にしており、死者の慰霊は一族で行うべきという通念を世間に浸透させた。
そして法事を適切に執り行えば彼岸の死者の魂は平安を得られ、この世に生きる者や将来の子孫を守護してくれる憐れみ深い祖霊になると信じられている。
徳川時代(1600-1867年)には、全世帯が檀家制度に登録することが求められ、最寄りのお寺で法事をするよう指示された。
「檀家」というのは、特定のお寺に帰属し、そのお寺を支える世帯のことだ。
日本では伝統的に、個人が信仰を選択するという観念は弱く、それぞれの世帯が代々属してきた仏教の宗派に帰依するのが普通である。
檀家制度は法的には19世紀に廃止されたものの、その痕跡は色濃く残っている。
また世間一般の信心では、死者の霊魂はこの世とのつながりを保持しているので、適切な法事を執り行うことで、死者の魂はこの世に生きる子孫や一族の将来を守護する善なる先祖になれる。
従って各世帯の構成員は、他界した霊に丁重な祭事を行い、それによって彼岸の親族縁者に平安をもたらすことが求められる。
それゆえ、高齢世代は自分たちが先祖供養をしてきたように、子孫も自分たちの死後、法事や慰霊を抜かりなく行ってくれることを願い、それを重要視しているのだ。
しかし現在では、仏教を支える基盤が徐々に失われつつある。
特に社会構造が変化し、近代化した世相の中で先祖や死後の世界への観念は弱まり、宗教の影響力が薄くなってきた。
それでも伝統を重んじる家族には、先祖崇拝の義務を維持し、個々人の考え方はさまざまでも社会単位である世帯のしきたりには従うべきであり、それによって親や祖父母を安心させるのが人の道だ、という感情が底流にある。
そのため、新しい信仰を持つか仏教を拒否した人でも、先祖を祭る家族の流儀を守ることが期待され、世間一般もそれを当然と感じている。
神道や仏教への関与は社会慣習やしきたりに基づくものであって、個々人の悟りや信念に由来するものではない。
このため多くの日本人は世論調査などに「宗教を持たない」と回答する傾向がある。
これは特定の信条や宗教を信奉していない、という意味であって、そう回答した人でも死者を祭る仏事に参加し、地元の神社のお祭りや元旦の神社参拝には行く、と答えるはずだ。
人々は神道や仏教の行事を執り行うことに矛盾を感ぜず、そうした行為自体は特定宗教への帰属や信仰を意味しない。
実際、個人としての信仰の有無が、伝統的な宗教行事に参加する際に妨げとなることはなく、逆に個人の宗教的信念を盾に、伝統行事への参加を拒否すればいぶかしがられるのがオチだ。
新宗教、キリスト教、代替宗教の出現
19世紀初めから日本では新たな宗教運動が起き、その多くはカリスマ的人物がお告げを受けたり霊眼が開いたりして始まった。
のちに「新宗教」と総称されたこれらの運動も、既存の宗教文化に由来するものが多い。
仏教から抽出された観念を用いたものや、神道の特定の神と関連したものなどだ。
新宗教は一般人の処世に助けとなる霊的手法を体得させたり、魂の救いに新境地を開いたりした。
新宗教は一種の折衷なので極めて多種多様だが、共通性も有している。
(「新」とは、神道や仏教など既成宗教と対比して言う概念だ。
)新宗教は個々人にアピールし、彼らの多くは創始者のカリスマに魅了されたり、霊的癒しを得たり、人生の成功や救いに新たな道を開く教えに惹かれたりした。
新宗教に改宗した人が、伝統的な社会的義務を放棄すれば問題になるが、たいがいの新宗教は現存する社会や文化の規範に対立せず、むしろ信者に対して、仏教の法事や神道の祭儀に参加するよう促すのが常である。
その限りにおいて多くの新宗教は、社会全般の規範に適合して問題を起こさないよう配慮してきた。
それでも新宗教の評価は全体的に芳しくなく、社会から疎外され、中傷の的になりやすかった。
その理由は、一部の新宗教が日本の宗教秩序や社会制度に改革を迫り、伝統を蚕食しそうになったからである。
新宗教はマスコミや既成宗教の側から「似非信仰」と非難されることもあったが、それは既存の制度を揺さぶり、社会の一体性を崩しかねなかったからだ。
新宗教の創始者(彼らの多くは、力ある神々により抜本的な世直しや魂の新文明を創るために選ばれたと主張した)は、往々にして極端かつ理不尽な人物として描かれた。
特に19世紀後半から20世紀初頭にかけて爆発的に普及した宗教運動は、体制側に深刻な不安をもたらすものが少なくなかった。
例えばカリスマ的な出口王仁三郎に率いられ数百万人の信徒を獲得した大本教は、日本の既成秩序を痛烈に批判し、社会・精神的な変革を主張した。
この大本教などいくつかの新宗教が、戦前の国家体制に挑戦したという嫌疑をかけられて弾圧された。
新宗教が国家の干渉や統制から自由になったのは、戦後の新憲法の下で信教の自由が保障されてからのことだ。
たいがいの新宗教は社会の慣例に同調し、信者に対して伝統的な義務を果たすよう指導した。
だが数は少ないが独自路線をとるものもあり、それらの教団は物議を醸すだけでなく、新宗教の代表であると世間から(いささか誤って)見られるようになった。
そうした例の一つが日蓮宗の信徒団体である創価学会だ。
同会は戦後急速に成長して日本最大の宗教運動になった。
急拡大の時期には、日本の全世帯を折伏して仏法に基づく国造りを行うと豪語した。
こうした統治理想が激烈な折伏活動に拍車をかけたが、その反面、学会への苦情も多く寄せられた。
同会の排他的性格は信者を地域や社会活動から疎遠にさせ、国民に不安と嫌悪感を浸透させる結果となった。
学会はまた「公明党」を結成し、国会に議員を輩出し、つい最近まで連立政権のパートナーだった。
こうした政治的関与は創価学会にとっては価値のあるものだったが、一般国民には学会の野心に対する疑念を抱かせ、敵意のうねりを引き起こした。
同様に、重要な文化的インパクトを持つ一方、社会に不協和音をもたらしかねなかったのがキリスト教の日本伝来である。
キリスト教は16世紀初めに伝えられ、わずかの期間にいくつかの大名領地で信者が増えた。
しかしキリスト教は日本の統合と独立にとって脅威だとの不安の高まりを受けて禁教令が布かれた。
(そうした不安があおられたのは、アジアの国々が植民地支配される際にキリスト教が共謀しているとの認識が日本で広まったことにもよる。
)19世紀半ばに日本が開国政策に転じると、キリスト教は再び公然とやって来て、カトリックやプロテスタント諸派が布教に尽力した。
教育事業(=学校経営を通じ日本のエリート層に一定の同調者を得た)および社会福祉事業を通じて影響力を確保した。
しかしキリスト教は全般的に日本で成功せず、教勢も低いレベルにとどまった。
その主要な理由は、キリスト教が祖先崇拝を排除して、日本の宗教文化に挑戦したり伝統的に重要とされる事柄と衝突したりしたためであり、唯一なる全能の神を過度に強調したためだった。
「一神教は八百万(やおよろず)の神々を信心する日本人にはなじまない」「カトリックであれプロテスタントであれ、特定の信仰体系に従うのは多神教的なスタイルになじまない」と考えられた。
問題点と葛藤の所在:個人の信仰と慣習の拒否
キリスト教と創価学会の例が示すように、文化的同一性の強い環境に、特定の宗教が挑んできた場合、不安が生まれるのは当然である。
最近の日本社会でそうした問題が顕著になってきたのは、海外から入ってきた教団も含め新宗教の中に排他性を露わにしたり、家族や地域に根ざす伝統的な考え方や慣習を拒否したりする傾向が見えるからだ。
そうした団体が違法活動に走るなどして社会を不安に陥れる存在、あるいは治安を脅かす存在と見られるようになると、新宗教に否定的な傾向が強くなり、他の宗教にも飛び火していくのだ。
最も決定的な例はオウム真理教である。
この運動は80年代に成長し、数は少なくても極めて献身的な信徒グループを作りだした。
信徒の多くは高等教育を受けているが、現代の唯物的風潮からは疎外された若者たちだ。
オウム真理教は霊的指導者(麻原彰晃) への絶対的な忠誠を軸とした王政的共同体を作り、信徒には家族を捨てさせ、名字を放棄させ、所有物一切をオウムに寄付させ、修行共同体を形成し、オウムの「ホーリーネーム」を持つよう指導した。
教団のこうした要求がもとで信者の家族と葛藤が起き、入信した子供との面会を求める家族との間で裁判闘争まで起きた。
法律上は成人になれば信仰の自由が保障されている。
だが、世論は明らかに親たちの側に立った。
オウムが信者の親たちのみならず、教団施設のある地域社会と色々な葛藤をもたらし、オウムに批判的なマスコミや弁護士たちと闘うことになった時、教団と社会全般との緊張はさらに高まった。
こうした状況の中で、オウム側は現代の物質文明を崩壊させ、世界の霊的改革をもたらし、社会の体制と闘うという信念を強め、一層暴力的に走り、それが1995年の東京地下鉄テロ事件につながった。
一宗教団体が大量殺人を企て、国家の干渉から宗教を保護するはずの法律を隠れ蓑にし、宗教団体の非課税特権を悪用して極秘の化学兵器開発資金に充てた証拠が発見されるに至った。
この事件は宗教の自由をどこまで認めるべきかについて、広い議論を喚起した。
さらに宗教団体を公安機関がどこまで監視すべきか、宗教団体の資金集めや布教活動の範囲等についても論議を呼んだ。
多くの世論調査では、宗教団体が公共の場で布教することに反対意見が広まり、公権力が宗教団体への監視を強めることが広範に支持されている。
オウム事件をきっかけに、社会規範に挑戦し排他的な考え方を持つような宗教団体をどうするか、論議が喧(かまびす)しくなった。
国民の多くは、オウム信者が運動にのめり込み、社会と過激に対決するようになったのは、何らかの洗脳を受けたからだと主張した。
特にオウム信者たちが肉親を遠ざけ、オウムの施設に移り住み、その指導者に生涯の忠誠を誓い、ついには指導者の教唆で殺人を犯すこともいとわないまでになったのは、洗脳またはマインド・コントロールのせいだと考えるようになった。
洗脳とかマインド・コントロールといった主張には経験科学的な根拠はない(調査によればオウム信者は自発的に入信し、マインド・コントロールによらず、自ら積極的に活動に関与した)。
だが、オウム事件の余波で世間の風潮は次の二通りの展開を見せた。
第一に、いかなる宗教団体であれ(特に家族や社会の慣習を拒否し、一つの教条に全面的な忠誠を求める宗教団体には)、それに関わることは「危険な」ことと見られるようになった。
こうした見方はオウム以前にも存在したが、オウム以後は一層強くなった。
第二に、そうした宗教団体に加入する人は心理操作を受けているに「違いない」と見られるようになった。
この見方は証拠に基づくというよりは憶測に基づいているのだが、説得力があり、日本に激烈な反カルト運動を広めて、「カルト」(この単語は、日本では社会的規範から逸脱し既成宗教から離れた運動を広く指し示す)に関わった人々を「救出」すべきと考えられるようになった。
こうした問題は、特定の宗教運動が明確に社会規範を拒絶したり(統一教会の肉親に対する態度やエホバの証人の輸血拒否など)、家族による死者の供養を忌避したりしたため、格別な論議を呼ぶことになった。
そうした状況に置かれた両親にとって、法事に出席しない子供は、慰霊や供養を行う両親の目から見て罰当たりな存在なのだ。
個人の権利や宗教選択の自由と、地域や家族を軸にした慣習との葛藤は、子供が成人に達しても親の権威に服すべきだという隠然とした考え方とともに、現代日本の宗教事情をめぐる重要な議論の的となっている。
結語
日本における宗教の多様性という伝統は、各宗教間の相互作用や、多くの共通基盤を持つ枠組みの中で機能してきた。
それらの宗教を信じるにせよ信じないにせよ、文化的社会的な理由から、宗教行事やしきたりに従うことが期待されてきた。
そこでの帰属性は、個人の信念より集団の連帯感に根ざしていて、そこから個人の自由という法的立場との間に一種の対立関係が生じるのだ。
ただ、全般的に宗教間の違いは比較的上手に処理されていて、たいていの新宗教は教団への忠誠と、家族や地域の義務に従うことのバランスを巧みに取っている。
ある教団がそうした社会慣習を踏み外すと、その信徒の親たちは死後の供養をしてもらえないと憂慮し、社会一般も常識はずれの危険な宗教を嫌がるようになる。
そうした傾向は1995年のオウム事件以来、極めて一般的なものになっている。
問題のある教団(社会の支持する規範を拒否する団体)に入会する人は心理操作を受けているはずだという世間の憶測によって、法的に保障されている個人の権利の観念と、世間や社会の慣習の間に、摩擦と緊張が生じるのだ。
こうしたことが、社会慣習に挑むような教団に入った人々を世間はどう扱っているか、またそうした運動が日本社会でどう見られているかという論点についての中心的な検討課題になっている。
イアン・リーダー氏は四半世紀にわたって日本の宗教を研究し教えてきた。 日本やハワイ、スコットランド、デンマーク、イングランドの大学等で宗教と日本の研究に従事してきた。 1999年から2006年までランカスター大学で宗教学教授、2007年からマンチェスター大学で日本学教授、2012年にはランカスター大学に宗教学教授として戻る。 現代日本の宗教活動に関する書籍や論文が多いが、最近では1995年に東京地下鉄テロ事件を起こしたオウム真理教と、それが日本人の宗教観にいかなる影響を与えたかを研究している。