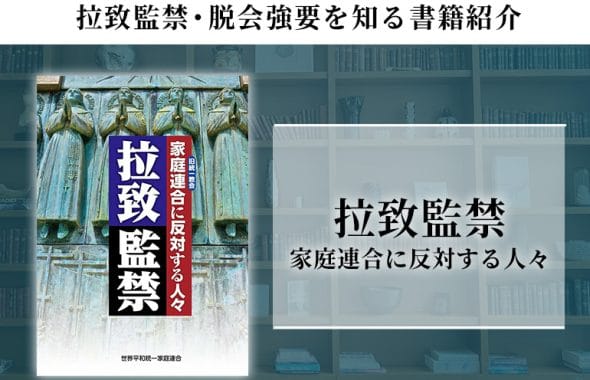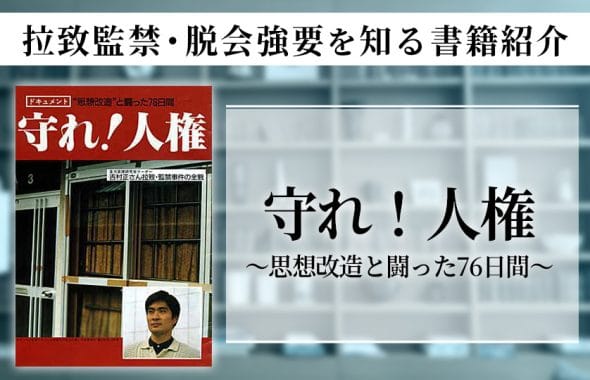📖なぜ福音派牧師が強制改宗をするのか? 監禁牧師による統一教会批判に答える
キリスト教牧師、特に「福音派」は、聖書を文字通り解釈し統一原理は間違っていると批判します。
ひいては監禁現場で、家庭連合信者に対して教義が間違っていると、福音派への改宗を迫ります。
しかしキリスト教は教派によって、多様な聖書解釈があるのが現状です。
本書では、統一原理が聖書をどのように解釈しているか福音派の考えと比較して、詳しく解説しています。
宗教者は互いの信仰や教義を尊重し理解を深めあうのがマナーであり、他宗教を自分の教義に基づいて批判したり押し付けたり、ひいては、拉致監禁などという卑劣な行為は絶対に行なってはならないものだと考えています。
本書「強制改宗をくつがえす統一神学」をご覧いただければ、福音派牧師による強制改宗や脱会説得がいかに不当なものなのかご理解いただけるものと思います。
- 神明忠昭博士がキリスト教による統一教会批判に答える
- 電子ブック版
- テキスト版
神明忠昭博士がキリスト教による統一教会批判に答える
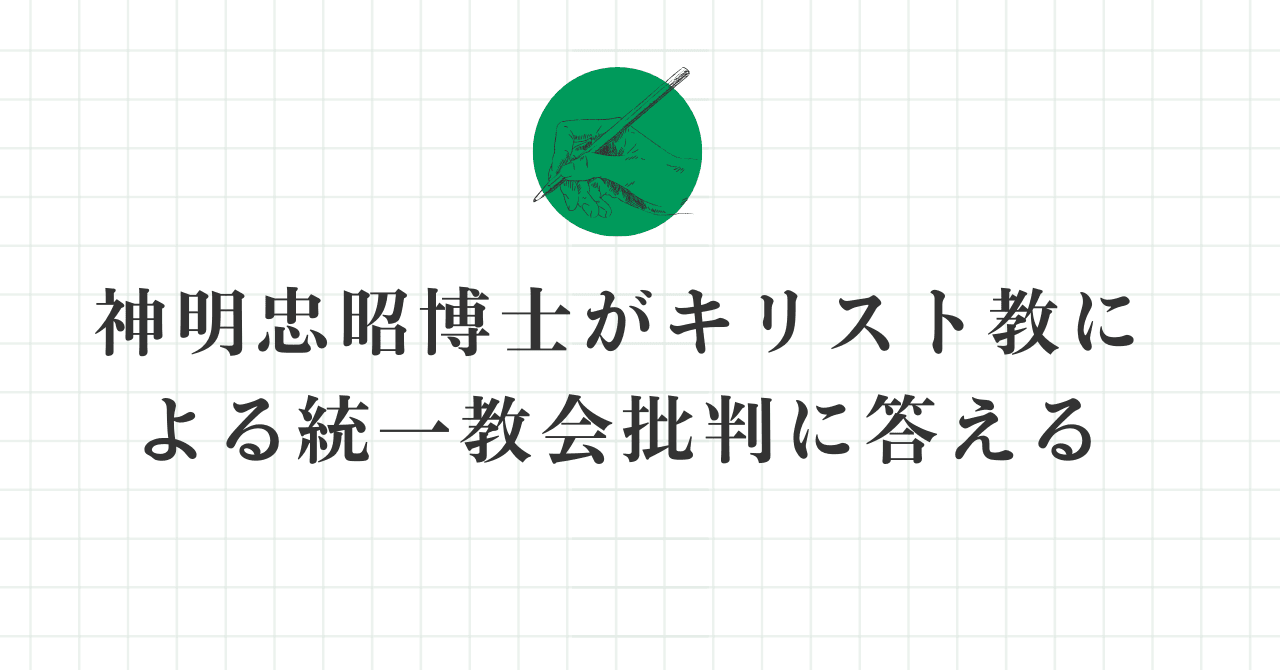
統一教会信者に対する拉致監禁・強制改宗に携わっている牧師たちは、統一教会の信仰が「異端」であるということをその活動の動機としています。
とりわけ「福音派」と呼ばれる、聖書を文字どおりに解釈する教派の牧師たちは、統一教会がキリスト教を名乗りながらも聖書をでたらめに解釈して人々を惑わすので、その信者に「正しいキリスト教」を教えてあげることが救いであると信じて疑いません。
そのため、彼らは監禁の現場で自らが寄って立つ福音派の神学に基づいて統一教会の教えである「統一原理」を批判し、信者の信仰を破壊しようと試みます。
神学に対する専門的な知識を持たない一般の信者たちは、こうした牧師たちによる統一原理批判に対して答えられないばかりか、外部との接触を完全に遮断され、長期監禁・説得をうけるという異常な環境下のもので、彼らの教えこそ「正しいキリスト教」であり、統一原理はでたらめであると思い込まされて信仰を失ってしまう場合が少なくありません。
しかし、キリスト教神学に対する広範な知識があれば、こうした批判が的外れなものであったり、非常に偏った立場からの批判であることが分かり、逆に福音派の神学との比較を通して統一原理の神学としての真価が再認識されるのです。
このたび、キリスト教神学を専門的に学ばれ、米国ニューヨーク州にある統一神学大学院で神学を講じている神明忠昭博士が、主に福音派の反対牧師による統一教会批判の代表的な12項目に対して答えながら、福音派の神学の限界と統一原理の価値を明らかにする論文を特別に寄稿してくださいました。
この論文を通して、反対牧師の説得によって統一教会を去った兄弟姉妹の皆さま、監禁から生還したものの統一原理に対する疑問を抱いている信者の皆さま、そうした信者たちを信仰指導する牧会者の皆さま、そして広く一般の皆さまに、統一原理のもつ神学的な価値を再認識していただければ幸いです。
電子ブック版
こちらの電子ブックは、今からテキスト版として書かれている内容をPDFブックとして公開しているものです。
本のようにめくりながら読んで頂けます。
電子ブック版かテキスト版どちらか読みやすいほうで是非お読みください。
テキスト版
目次
0.序言
1.聖書の権威を否定しているという批判
2.理性によって神を知るのは傲慢だという批判
3.神の悲しみの教説は神の完全性に反するという批判
4.霊界の存在を信じるのはオカルト的だという批判
5.アダムとエバの堕落の性的解釈は間違っているという批判
6.神の絶対予定を否定しているという批判
7.カルヴァン主義の五特質 (TULIP) に反しているという批判
8.人間を神扱いしイエスを人間扱いする傲慢で冒涜的なキリスト論だという批判
9.自力信仰であるという批判
10.十字架贖罪を否定しているという批判
11.真のご家庭に対する批判
12.社会問題を引き起こす悪なる団体だという批判
序言
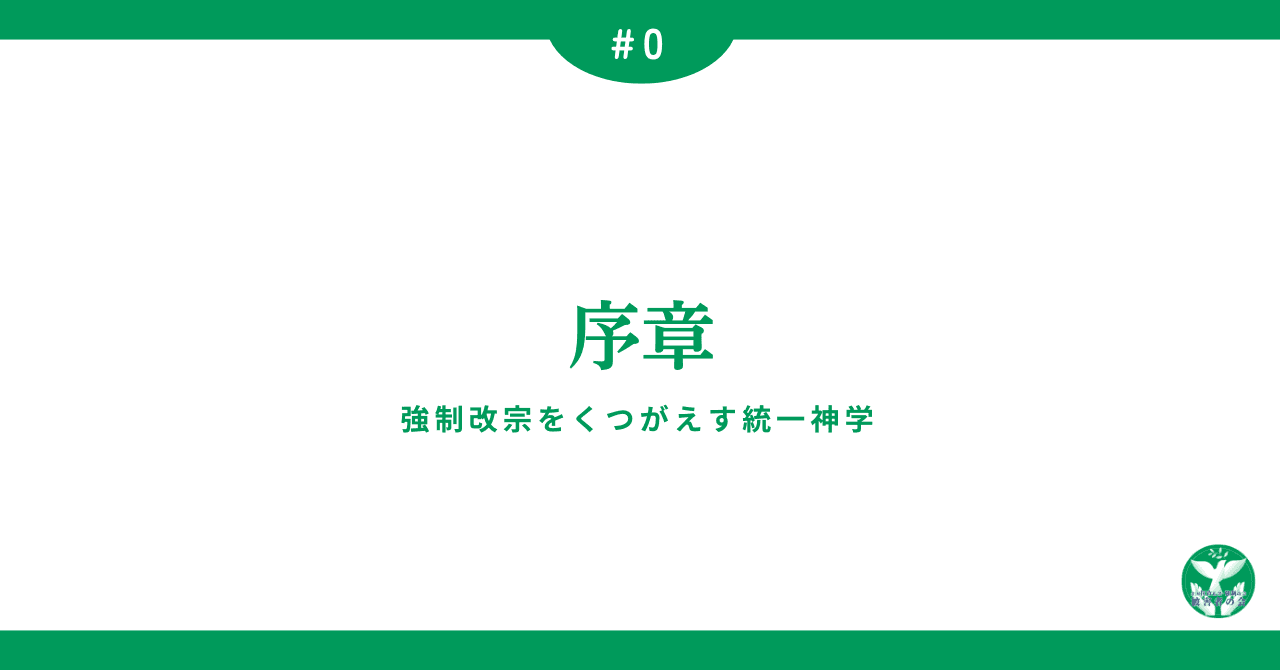
日本統一教会のメンバーを拉致監禁して強制改宗をしようとするキリスト教牧師、特に福音派の牧師から出される統一教会批判は様々あるが、この小冊子はその中の代表的な12の批判を選んで、それに対して統一神学の立場から答えるものである。
それによって、如何にキリスト教による統一教会批判が、福音派的信仰の名の下に狭い視野からなされ、統一教会の教えである統一原理を頑ななまでに曲解するのみならず、聖書に基づくキリスト教の全体像とその歴史の発展的な流れに反し、更には、神の本質までも否定して神を逆主管する間違いを犯しているか、を露わにしてみたい。
これを通して、統一教会のメンバーは勿論のこと、反対牧師、強制改宗の被害者にも、統一原理の正当性と将来性を理解して頂ければ幸いである。
信教の自由を奪う拉致監禁・強制改宗は法的にも許されないが、強制改宗の神学理論の間違いも放置できない。
統一神学こそ強制改宗を神学的にくつがえし更にはキリスト教を導く力を持つ。
なおここで、統一神学とは、今までのキリスト教神学の中に生じて来た様々な未解決な問題点を、統一原理を応用しつつ解決して、新しい時代を導く神学的ビジョンを作り上げる新しい組織神学であることを付記したい。
統一原理の『原理講論』は1995年出版の第2版第1刷を使わせて頂いた。
2010年2月吉日 米国ニューヨーク州アーヴィングトンの寓居にて 神明忠昭
聖書の権威を否定しているという批判
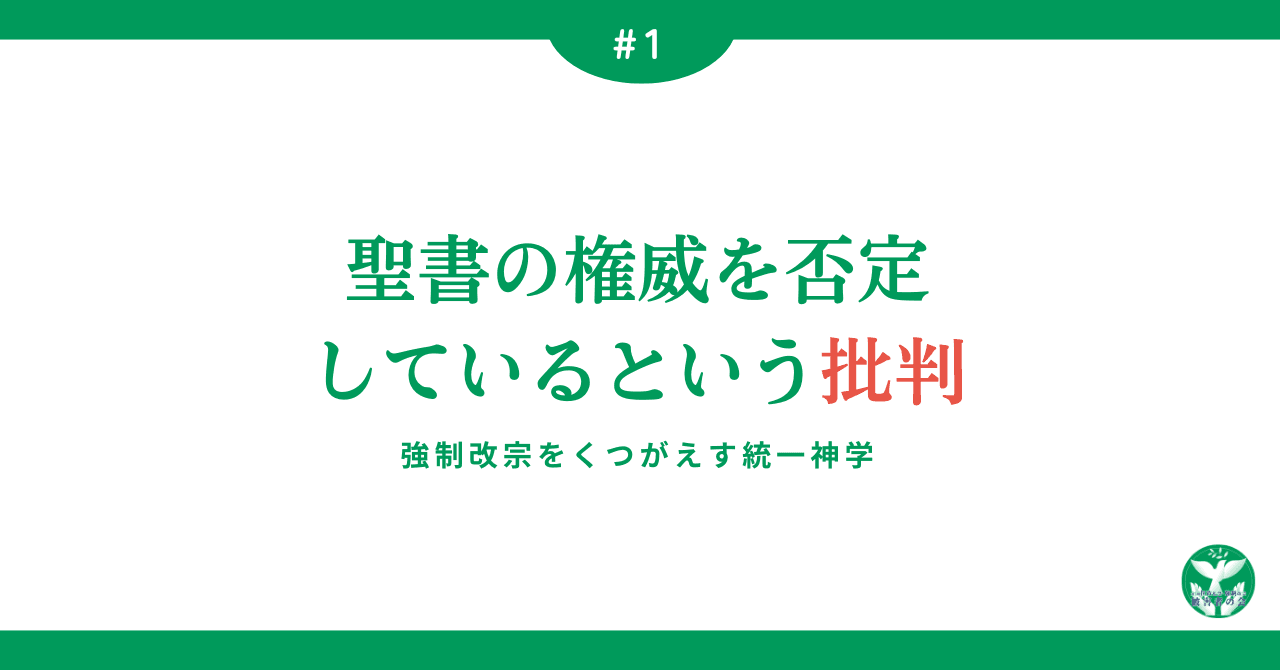
統一教会の『原理講論』は、聖書は神の永遠の真理それ自体ではなく「真理を教示してくれる一つの教科書」なので、聖書を「不動のものとして絶対視してはならない」と述べている (30頁)。
それゆえ、特に福音派は、統一教会は聖書の権威を否定し聖書を冒涜している、と批判する。
しかし、聖書の権威といっても様々な見解があるのが事実であり、福音派の見解のみが正しいという保障はどこにも無い。
統一教会の見解は聖書の権威を立派に認めているし、その見解は多くのキリスト教徒の見解と共通している。
かえって福音派の見解の方に大きな問題がある、と指摘するキリスト教徒は多い。
福音派は聖書の「逐語十全霊感」(verbal plenary inspiration) を信じる。
これは神の霊感の程度を示す「逐語霊感」(verbal inspiration) とその範囲を表す「十全霊感」(plenary inspiration) を合わせたものである。
だから聖書の写本や訳本は別としても、元々の聖書記者たちによる原典全体にわたって、科学や歴史に関する記述をも含めて、その一字一句の文字の表現に誤りが無いはずであり、そういう意味で聖書は「無誤性」(inerrancy) を持つという。
それゆえ、聖書は神の永遠の真理それ自体であり、絶対的権威を持つという。
「内容」と「表現」の見解
しかし、キリスト教におけるもう一つの代表的な見解は、福音派の見解とは違い、「内容」としての神の真理とそれを「表現」する聖書の文字を一応区別し、聖書の権威は「表現」としての文字それ自体にあるのではなく「内容」たる神の永遠の真理にあるとする。
この「内容」と「表現」の区別は分離、隔離ではなく、二者一体の中における区別である。
この区別は、神 (セオスθεός) という「内容」を我々の言葉 (ロゴスλόγος) で「表現」したものが「神学」(セオロギアθεολογία) であるというギリシャ語の「神学」の定義の中の二者の区別にも見られるように、キリスト教神学では常識中の常識である。
聖書は神学的だといえることや、聖書神学という分野が存在することからして、聖書にもこのような神学の定義が当てはまるのは当然のことであろう。
だから聖書が神の霊感によるものであっても、その文字の「表現」は人間が係わっているので完全ではないはずであり、特に科学や歴史に関しては間違いがあるかもしれない。
でも、文字の背後にある神の真理とか信仰の「内容」には誤謬が無いはずなので、それを「無謬性」(infallibility) と呼び、福音派のいう文字の「無誤性」(inerrancy) とは違った意味を持たせる。
これによれば、聖書の権威はまさにこの「内容」としての神の真理の「無謬性」にあるのであり、福音派のいう聖書の文字の「無誤性」にあるのではないという。
無謬性を認めている原理講論
同じように統一教会の『原理講論』も、聖書が神の真理を教示する一つの教科書であるという時、「表現」としての教科書の背後にある「内容」としての神の真理は「唯一であり、永遠不変にして、絶対的なもの」(30頁) であるとみなし、神の真理自体の「無謬性」をはっきりと認めていることに注目されたい。
統一教会は聖書の権威をここに見いだす。
だから文鮮明師も特に若かりし時に、聖書の紙が擦り切れてボロボロになるほど真剣に読まれた。
背後の無謬なる神の真理を把握することによって人間の諸問題を解決するためであった。
多くの信仰的なキリスト教徒と同様に統一教会は、聖書は福音派のいう「逐語十全霊感」や文字の「無誤性」によるものでなくても、やはり神の真理の書として神の霊感の下に書かれているので、聖書を読む時に聖霊の力を受けて読めば、文字の表現の背後にある神の永遠の真理を受けることができる、と信じる。
だから、福音派は福音派以外の信仰者を一緒くたにリベラル派呼ばわりをしてはならない。
聖書が神の霊感によるものであるということは、聖書自体もそういっているので、キリスト教の歴史の出発点より受け入れられて来た。
しかし、福音派のいう聖書の文字の「無誤性」の説は初めからあったわけではない。
それがキリスト教の中で正式に主張されるようになったのは、18世紀の啓蒙主義に対する反作用として福音派が出現して、特に「逐語霊感」が以前より強調されてからのことである。
特に20世紀になってアメリカの福音派の中でそれが盛んに強調され、1978年には「聖書の無誤性に関するシカゴ声明」(The Chicago Statement on Biblical Inerrancy) が発表された。
勿論、16世紀の宗教改革はカトリック教会の権威に反対して聖書の福音を重んじたので福音的であったとはいえるが、今の福音派のように聖書の文字の「無誤性」を説いたわけではない。
宗教改革の基本原理である「聖書のみ」(sola scriptura)、 というのは「形式原理」として聖書の重要性を訴えているだけであり、その文字をそのまま神の真理として絶対的に受け入れよ、というのではない。
むしろ聖書の中にある「内容原理」である神への信仰を受け入れよ、というのである。
20世紀の「新正統主義」を代表する偉大な神学者カール・バルト (Karl Barth) も、聖書のウルクンデ (Urkunde 文書) の背後にある神というザッヘ (Sache 事柄) を受け入れることの重要性を説いた。
福音派の聖書観2つの大きな弱み
福音派の聖書観には少なくとも二つの大きな弱みがある。
一つは、その「逐語十全霊感」の説が、聖書全体の一字一句が神の霊感によって書かれたと説くので、神の口述を聖書記者がワープロかロボットのように機械的に筆記したという悪名高い「口述筆記説」(dictation theory) と同じに見えることである。
「口述筆記説」はファンダメンタリスト(根本主義者)だったら受け入れる者がいるかもしれないが、福音派はやはりそのような説を奉じているとは見られたくないので、ある程度、聖書記者の参加を神の霊感とのダイナミックな関係でとらえる「動力霊感」(dynamic inspiration) なるものを考える。
これによると、神はその霊感で以って、聖書記者の持つ個性、語彙、文法の知識などの枠組みから一番適切な言葉を選んで、聖書の一字一句を構成して行くというのである。
しかしこれでは、聖書記者が人間として初めから持っている不完全な枠組みが土台になっていることになり、結局は、元々の文字の「無誤性」を捨てるような矛盾に突き当たるのではなかろうか。
福音派の二つ目の弱みは、聖書の文字の「無誤性」が偶像崇拝的な立場を持つということである。
この「無誤性」は、聖書の文字をそのまま永遠、不変、絶対の神の真理と見なし、神でないものを神としてしまうからである。
信仰的なキリスト教徒の福音派に対する批判
だから、有名なエミール・ブルンナー (Emil Brunner) を初め他の多くの信仰的なキリスト教徒は、福音派が聖書を「紙の教皇」のように偶像崇拝している、と批判した。
この批判をかわすために、福音派は「無誤性」といっても「絶対無誤性」(absolute inerrancy) ではなく「十全無誤性」(full inerrancy) の方を奉じているから大丈夫だという。
ファンダメンタリストが信じるような「絶対無誤性」の立場は、歴史や科学についての記述も現代人の尺度からして絶対に正確であると説く。
一方、福音派の「十全無誤性」の立場は、歴史と科学についての記述は現代人から見ると必ずしも正確 (exact) ではないが、当時の聖書記者たちからすれば完全に真実 (fully true) であり無誤 (fully inerrant) だったはずなので、いずれは正確でない部分の説明がつくという。
しかし、このような批判のかわし方は、結局、「表現」としての聖書の文字がやはりある意味で不完全だと認めることになり、再び「無誤性」を捨てざるを得ない矛盾に突き当たるのではなかろうか。
理性によって神を知るのは傲慢だという批判
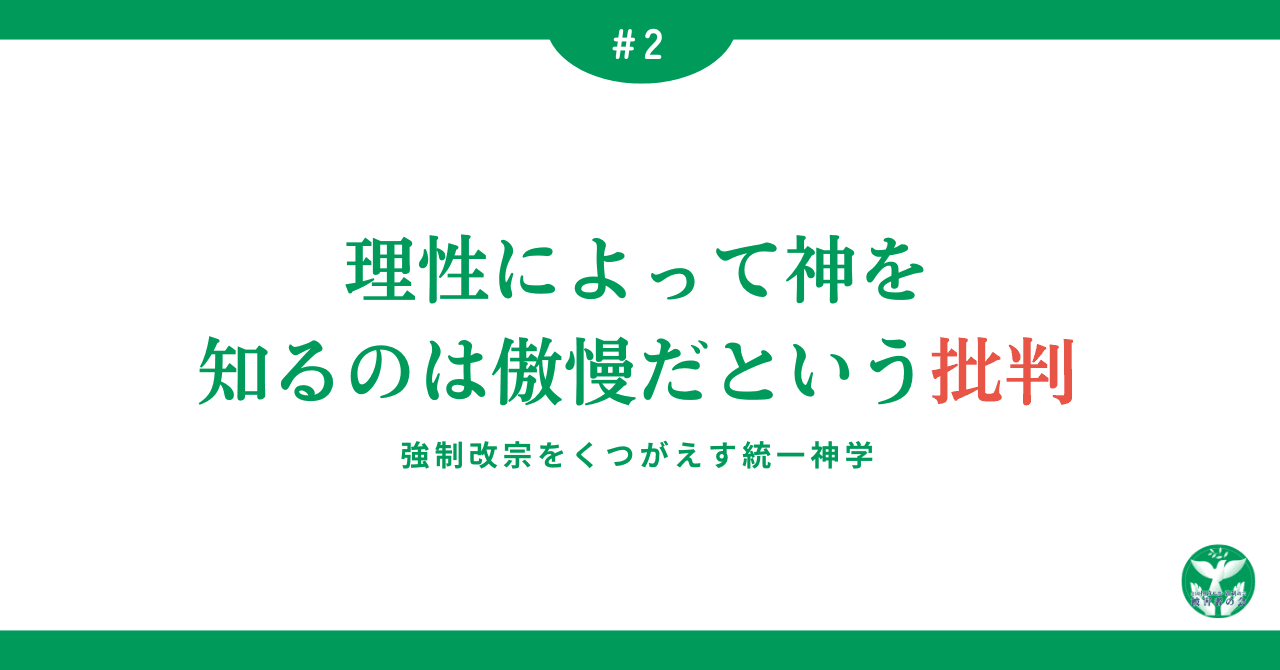
『原理講論』の創造原理は、作品を見て作者の性質を知ることができると同じように、神の作品である被造世界を見ることによって神について知ることができる、と述べている (42頁)。
これに対して、特に福音派は、信仰の次元で神の一方的な啓示によってしか神を知ることはできないのであって、被造世界を見て、分析して、人間の理性で以って神を知ろうとするのは傲慢である、と批判する。
確かに、信仰が一番重要であることは殆どの信仰者が認めることではあるが、キリスト教全体を見ると、理性の役割をも認め評価する多くの信仰者がいることも事実である。
だから信仰のみを重視し理性を無視する福音派だけが正しいという保障はどこにも無い。
実は、統一教会の教えは、福音派が批判する人間の理性の役割だけではなく、それ以前に神の啓示を受ける信仰を持つことの重要性についても述べている一つの膨大な体系なのである。
先ず、統一教会が如何に神の啓示を重視し、またそれを受けることのできる我々の信仰の重要性を説いているか、を見てみよう。
それを見れば、信仰を重んずる福音派がうなずけるところもあると思う。
統一教会の信仰の重要性
統一教会は、計り知れない神と神のみ旨については決して人間の理性や分析を通して知ることができるものではなく、信仰を通して神から受けるものである、と考える。
だから『原理講論』も、「人間を生命の道へと導いて行くこの最終的な真理は、如何なる経典や文献による総合的研究の結果からも、また如何なる人間の頭脳からも、編み出されるものではない」のであり、「あくまでも神の啓示をもって」与えられるものである、と述べている (38頁)。
統一教会のメンバーであれば誰でも知っているように、文鮮明師は信仰生活のモットーとして「絶対信仰、絶対愛、絶対服従」をいつも強調される。
信仰によって自己を低くし無にして他人のために歩めば、大気圏で低気圧に向けて周囲の高気圧から風が流れ込んで来るように、神の啓示と神の援助が流れ込んで来る、というのが師の信念である。
しかしながら、文師の統一原理によれば、話はここで終るのではない。
何故ならば、人間が救いの過程で霊的に成長すれば、堕落によって失った「創造本性」を次第に復帰するからである。
この人間の「創造本性」は、キリスト教では創世記2:17 に見られる 「神のかたち」(Imago Dei) に相当し、これは神から本来与えられた理性、自由意志、授受作用の能力などであるとされる。
だから人間が霊的成長に応じて「神のかたち」が復帰され、その中の理性が復帰されて行けば、神を知る上での理性の役割が生じて来るはずである。福音派はこの点を見逃しているようである。
実際、キリスト教の歴史において、理性の役割が信仰との関係で論じられて来た。大別すると四つの見解がある。
キリスト教の信仰4つの見解
第一の見解は、神を知るのは信仰のみによるのであり、決して理性によるものではないとするパウロ、テルトリアヌス (Tertullianus)、宗教改革のルターなどの見解で、勿論、福音派もこの見解を持つ。
第二は、理性を信仰の土台の上に置き、先ず信仰があった上でその次に理性が働くようになるという12世紀初頭のアンセルムス (Anselmus) の見解で、彼が「知解せんがためにわれ信ず」(Credo ut intelligam) といった言葉はこの見解を端的に表している。
第三は、13世紀のカトリック神学者トマス・アキナス (Thomas Aquinas) の見解で、神の啓示を直接受ける信仰と、被造世界を分析することによってその創造者たる神を間接的に知る理性は、それぞれ独立したものではあるが、両者は矛盾せずに互いのために役立つ関係を持つという。
第四は、信仰と理性の完全統一を主張した18世紀の合理主義者ライプニッツ (Gottfried Leibniz) やスピノザ (Baruch Spinoza)、そして19世紀のヘーゲル (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) などの見解で、理性は信仰の内容を全部理解できるという。
このような様々な見解が存在するのは、人間がその信仰生活の中で霊的に成長すれば、堕落によって失われた理性が次第に復帰されて、神を知る上で理性と信仰とのギャップが次第に狭まって行くということを物語っていると考えられる。
理性が聖書のいう本然の「神のかたち」の一部として神から人間に与えられたものであるならば、それを無視してはならないであろう。
統一原理の「成長期間」の教え
統一原理は、人間は創造後に一定の「成長期間」を通過して完成することになっており、堕落後も救いの過程としてこの「成長期間」を通過することになっている、と教える。
だから、この成長期間の初期の段階では、理性の回復がまだごく僅かしかなされていないので、第一の見解のように信仰のみが強調されるだろうし、その後「成長期間」を通過しながら霊的に成長するに従って、次第に理性が回復されるので、第二、第三、第四の見解が次々と現れ、理性の役割が増長して行くのが認識されると考えられる。
このように、統一原理は信仰を出発点として四つの見解全てを包括する膨大な体系なのである。
だから、『原理講論』が、被造世界を見ることにより理性で以って神の性質を知ることができるという時、「成長期間」を通して信仰を通過したという土台の上に立っていっているのであり、決して傲慢な立場ではないことが分かるであろう。
統一教会は、最終的には信仰と理性の統一、自然神学と啓示神学の統一、宗教と科学の統一が来ると表明はするが、信仰を初めから軽視するリベラル派とはこのように袂を分かつので、傲慢だという批判は当たらない。
神の悲しみの教説は神の完全性に反するという批判
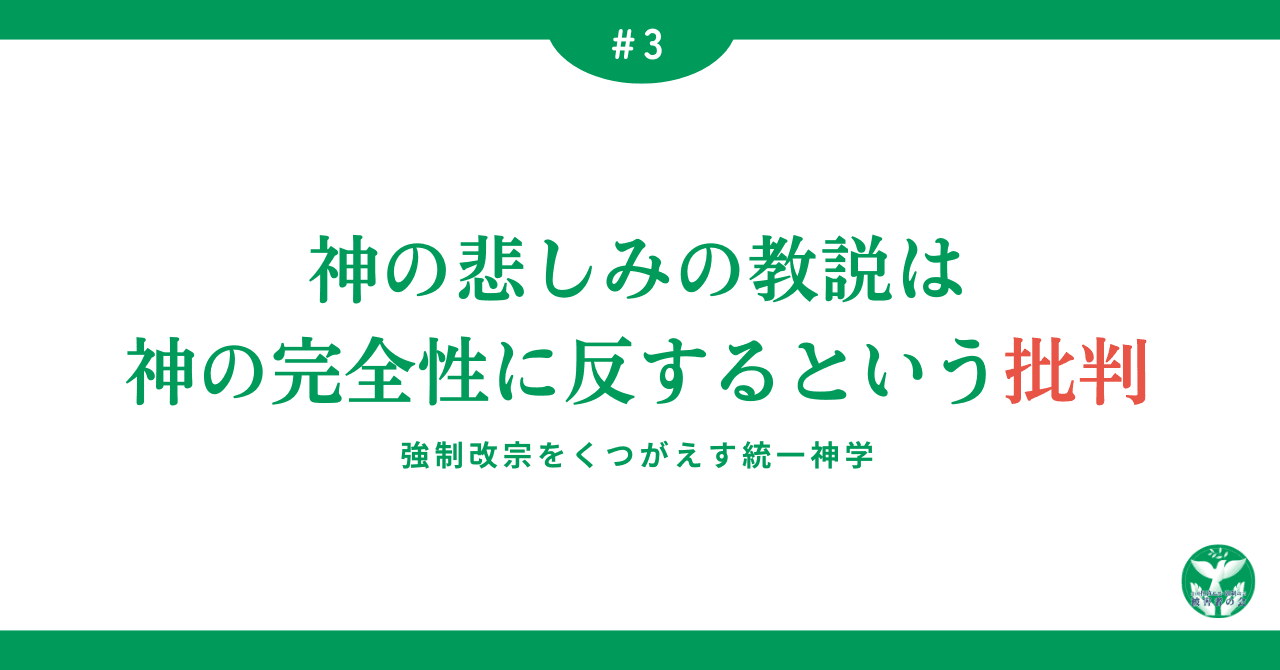
統一教会は、神は堕落した人間の悲惨な姿を見ながら、愛するがゆえに悲しみ苦しんで来られたと教える。
これに対して、福音派を初めとする既成のキリスト教神学は、神は愛の神であっても同時に完全な神だから、何からも影響や変化を受けるはずはなく、たとえ悲惨な堕落人間を見たとしても、それによって動かされて悲しみ苦しむような神であるはずはない、といって統一教会の教説を批判する。
既成のキリスト教神学のこの見解は、完全な神ゆえに同情することも悲しむこともできない一種の冷酷な神を示しているようであるが、これは決して筆者による誇張ではなく、実際、11世紀の有名なアンセルムスも、その著『プロスロギオン』8章の中でこの見解を自分の見解として述べている。
しかし現在では、キリスト教内部のあちらこちらで、この伝統的な見解が不適当であることが指摘され、神の悲しみについて見直される趨勢にあるのである。
ゆえに、統一教会の教説が正当だったといわれる時が来るのも近いであろう。
その大きな理由は、神の愛も含めて、真の愛とは、相手の悲しみと苦しみを感じなくとも一方的に何かを与えて満足するような愛ではなくて、相手の悲しみや苦しみに同情して自分も共に悲しみ苦しみながら何かをしてあげる愛である、ということが現在多くの人々に理解されるようになって来ているからである。
しかも、驚くなかれ、この真の愛についての新しい理解は聖書に基づいているのである。
真の愛についての新しい理解は聖書に基づいている
旧約聖書は神の愛ゆえの悲しみについて多く語っている。
創世記6:6 を見ると、神は、人間の悪が地にはびこったのを見て、「地の上に人を造ったのを悔いて、心を痛め」られたとある。
また、エレミヤ書 9:1 などには嘆きの神の涙が記されている。
だから20世紀最大のユダヤ教神学者エイブラハム・ヘッシェル (Abraham Heschel) も、1963年出版の著『イスラエル預言者』(原題The Prophets、日本語訳、教文館1992, 2004年出版) の中で、神との愛の契約関係を結んだイスラエルの民が神に叛いた時に、神が如何に悲しみ苦しまれたか、を預言者たちはよく知っていたと論じている。
新約聖書の背後にも神の悲しみが潜んでいると直観したのは宗教改革のルターであった。
マルコ伝 15:39 を見れば、イエスの十字架上での死の悲惨な光景を一部始終見た百卒長は「まことにこの人は神の子であった」と告白したとあるが、ルターはこのことゆえに、神の本当の性質はイエスの十字架のような苦難の悲しみの真只中にこそ見出され、それが神の愛ゆえの悲しみであるという「十字架の神学」(theologia crucis) なるものを提示した。
ルターのこの直観は、18世紀以来のリベラル派の神学では全く評価されなかったが、20世紀になり「新正統主義」のカール・バルトによって見直され、次第に教派を超えた大きな学派を世界的に形成するまでに至った。
プロテスタントではモルトマン (Jürgen Moltmann) やユンゲル (Eberhart Jüngel) など、カトリックではラーナー (Karl Rahner) やフォン・バルタザール (Hans Urs von Barthasar) など、それにロシア正教ではブルガコフ (Sergei Bulgakov) やベルジャーエフ (Nicolas Berdyaev) などがこの学派の流れを汲む。
『神の痛みの神学』を1946年に出版して世界に知られた日本の北森嘉蔵もこの流れの中に入る。
ついでに、福音派が忌み嫌うリベラル派神学も、その人間主義的傾向ゆえに、神の真の愛の中にある悲しみなど全然知らないし、知ろうともしない。
だから、これももう一つの皮肉であるが、福音派はリベラル派と全く同じ間違いを犯しているわけである。
では、何故このように既成のキリスト教は聖書の本質から外れた見解を持つようになってしまったのであろうか。
キリスト教神観のヘレニズム化
それは、キリスト教の神観が、初めから古代ギリシャ哲学の強い影響を受けて形成され、ヘレニズム化されたからである。
古代ギリシャのプラトン (Plátōn) やアリストテレス (Aristotélēs) は、聖書的な神の愛を知っていたわけではないので、この世界がいつも変化して不完全であるのに対して、神は不変で完全なる至高の存在であると割り切った。
特にアリストテレスは神を形容するのに「不動」(άκίνητον) という言葉を使い、何ものによっても動かされないことが完全であるという定義を下した。
キリスト教の神観は、この不変 (不動) イコール完全という単純図式の影響の下に形成されて、神の完全性の名の下に、神の愛から、共に悲しむ同情心の深みを取り除いてしまったのである。
しかし最近では、この図式は多くの神学者たちによって批判され、神の完全性の新しい定義が模索されている。
それによると、神の完全性とは単なる不変とか不動にあるのではなく、堕落人間から裏切られて悲しみ苦しんだとしても、それに屈せず、どんなことがあっても人間と再会することを切望する、消しても消えない愛の能力にあるというのである。
モルトマンは、その著『三位一体と神の国』の中で、このような神の「切望」(Verlangen nach) について述べている。
統一教会では、これを神の「心情」と呼び、「愛を通じて喜ぼうとする情的な衝動」と定義する (『新版統一思想要綱』53頁)。
これは「内部からわきあがる抑えがたい」心情なので (前掲書53頁)、途中では悲しみの心情であったとしても、いずれは神の願いを必ず成就する原動力となり、神の完全性と全能性を説明することにもなろう。
これこそ聖書的な神の愛の本質ではなかろうか。
聖書の奥義を誰よりも深く紹介した文鮮明師によれば、我々は今までの神の悲しみの心情をできるだけ早く喜びの心情に変えてさしあげ、親なる神を慰労する親孝行の道を歩む子女でなければならないというのである。
霊界の存在を信じるのはオカルト的だという批判
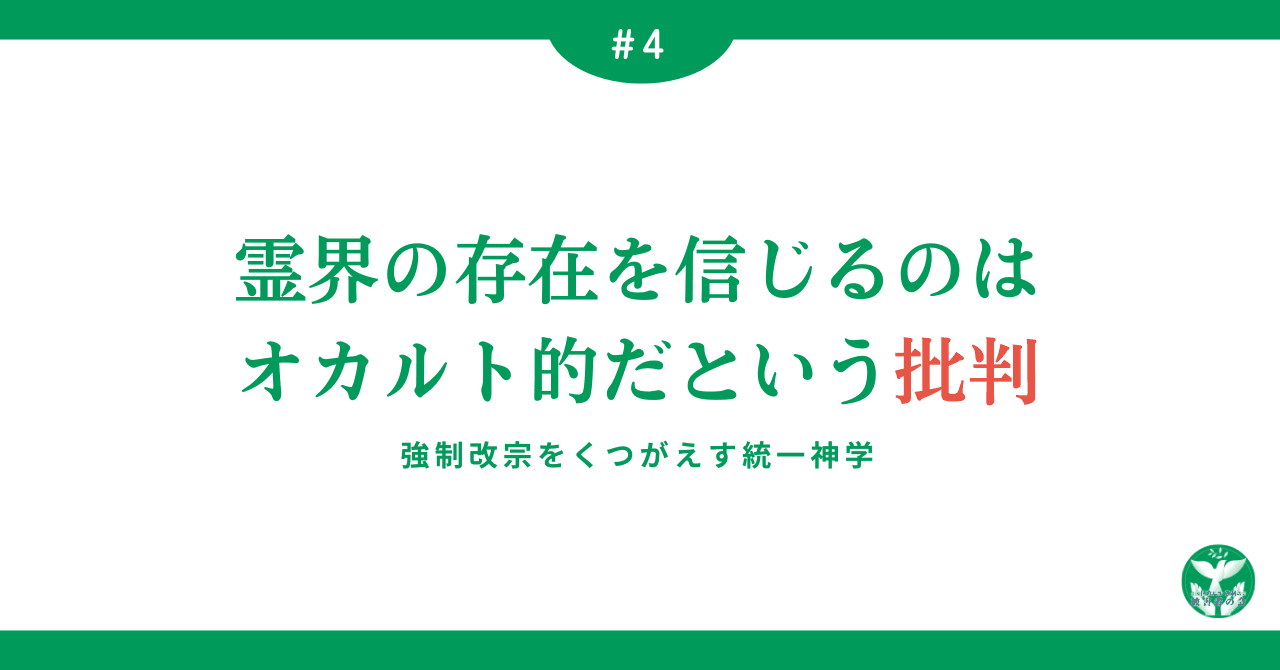
統一教会は霊界の存在を信じ、善霊や悪霊による霊現象について語り、いわゆる先祖解怨などもするので、霊界の存在を軽視する福音派を初めとする既成のキリスト教は、統一教会がオカルト的だと批判する。
しかし、新約聖書の福音書によると、2000年前のイエスご自身も、既に他界していたモーセやエリヤと変貌山で話をしたり、悪霊現象に対処して悪霊を追い出したりされている。
福音派を初めとする既成のキリスト教は、これをオカルト的とはいうまい。イエスの本来の願いを受けて立つ統一教会もイエスと同じように霊現象に対処しているのである。
霊界の存在を無視または軽視するのようになった2つの大きな理由
今までのキリスト教は、イエスご自身が霊現象に対処された事実を忘れて、霊界の存在を軽視または無視するようになってしまったが、それには少なくとも二つの大きな理由があった。
第1の理由
第一の理由は、もしアダムとエバが堕落しなかったならば、肉体の死は無かったはずであり、人間は地上に永遠に住むはずであった、と信じるが余り、死後の世界としての霊界の必要性をそれほど強く感じなかったからである。
それによると、勿論、実際には人間始祖の堕落により、肉体の死が天罰として起こるようにはなったが、しかし、その肉体の死はイエスの十字架による死と復活によって「滅ぼされた」ために、信仰者は肉体の死後も終末において「肉体の復活」にあずかる特典を受け (1コリント書15:20-26)、この肉体の復活がある限り霊界に関心を持つ必要がなくなる、というのである。
しかし、この論法には様々な無理がある。何故ならば、先ずこの論法によると、神はアダムとエバの堕落によって永遠の地上生活の可能性が無くなってしまった後に初めて霊界を創造されたことになるからである。
しかし、聖書には「はじめに神は天と地とを創造された」(創世記1:1) とあるように、(天と地がそれぞれ霊界と地上界を指しているかどうかの解釈の問題は別にしても)、少なくとも、神が初めから霊界と地上界の両方を含めた全ての被造物を創造されたと見るのが自然である。
次に、信仰者は肉体の死後も終末には肉体の復活を受ける予定なので、霊界に無関心になってしまうのであろうが、この論法によれば、肉体の死後すぐに肉体の復活があるのではなく、終末の時まで待たねばならないのだから、復活を待つその期間 (終末論では「中間状態」intermediate state と呼ばれる期間) は、少なくとも霊界での期間ではなかろうか。だから霊界を無視してはならないであろう。
もう一つの問題は、いよいよ終末が来て肉体の復活にあずかったとしても、その復活した肉体というのは、パウロが2コリント書15:42-44でいっているように、決して地上界で持っていたような肉体ではなく、あくまでも霊界の次元に属する朽ちない「霊のからだ」なので、肉体の復活後も、霊界での生活が続くはずである。
だから、この意味でも、霊界を軽視したり無視したりすることはできないはずであろう。
統一原理は、これらの無理難題を解決することができる。
『原理講論』によれば、神は、人間が堕落しなくても初めから霊界と地上界の両方を創造されたのであり、決して、人間堕落後に霊界を創造されたのではない (210頁)。
そして、人間の「肉身」は地上界での命を全うすれば死に、「霊人体」だけが霊界に行って永生するように創造されたのである (210-211頁)。
また、肉体の復活というのは、終末の時まで待たずに、「肉身」が死に「霊人体」が霊界に行くその瞬間に、「霊人体」の中に形状的部分として元々あった「霊体」(86頁) が前面に出て、それが体の役割を担い始めるという形で生じるのである。
この「霊体」はパウロのいう「霊のからだ」に等しい。
肉体の復活は終末まで待たずに、肉体の死の瞬間に生じることは、2コリント書5章にも記されているように、後期のパウロ自身も知っていた。
いずれにせよ、統一原理はこのように、初めから霊界の存在の重要性を強調する。
第2の理由
キリスト教が霊界の存在を軽視するようになった第二の大きな理由は、人間は肉体の死の瞬間、天国に行くか地獄に行くかが最終決定されてしまって、天国に行った人はそのまま天国止まりであり、地獄に行った人はもう霊的成長と救いのチャンスは皆無であり、霊界では原則的に何の活動も無くなる、という決定論主義的な考えがはびこっているからである。
ただ、終末になって肉体の復活があれば、天国に行った人の喜びはますます強くなり、地獄に行った人の苦しみもますます強くなるだけであり、その強くなった喜びあるいは苦しみは永遠に続くという。
しかし、この論法も実に深刻な問題を露呈している。
カトリックでは、「父祖の辺獄」(limbus patrum) に行った旧約時代の聖賢や「煉獄」(purgatorium) に行った人は「天国」に移行できる可能性をまだ持っている、と教えるが、それ以外は、カトリックでも、そして「父祖の辺獄」や「煉獄」の概念が無いプロテスタントでも、一旦「地獄」に行ってしまった人間を、その苦しみから解放する道は全く無いのである。
失われた一匹の羊をも捜し求める (マタイ伝18:12-14、ルカ伝15:4-7) 真の愛の神が、このような無慈悲な教えを果たして容認されるだろうか。
それで、キリスト教徒の中には、この問題を解決するために、霊界の救われにくい人にも救いの機会を与えようとして、東洋の輪廻思想をキリスト教の中に取り入れている者もいる。
しかし、統一教会は輪廻思想ではなく、霊界に行ってしまった救われ難い「霊人体」が地上人に「協助」して、地上人の立てる善の功績、功労を受けて次第に救われて行く道がある、と教える。
霊界の「霊人体」が霊的成長と救いを必死に求めることから来るこの「協助」現象ゆえに、霊界は決して静かではなく非常に活動的である。
だから、旧約聖書も、サウルが口寄せを通して霊界のサムエルと話したこと (1サムエル28:7-19) などの霊現象を記しているし、新約聖書も、既に述べたように、イエスにまつわる霊現象を多く報告している。
ついでながら、それ以外にも、聖書全体を通して、霊的存在である天使の活動も沢山報告されている。
キリスト教徒が、霊界の一部である天使界のこのような活動を信じるならば、霊界を軽視したり無視したりすることはできないであろう。
アダムとエバの堕落の性的解釈は間違っているという批判
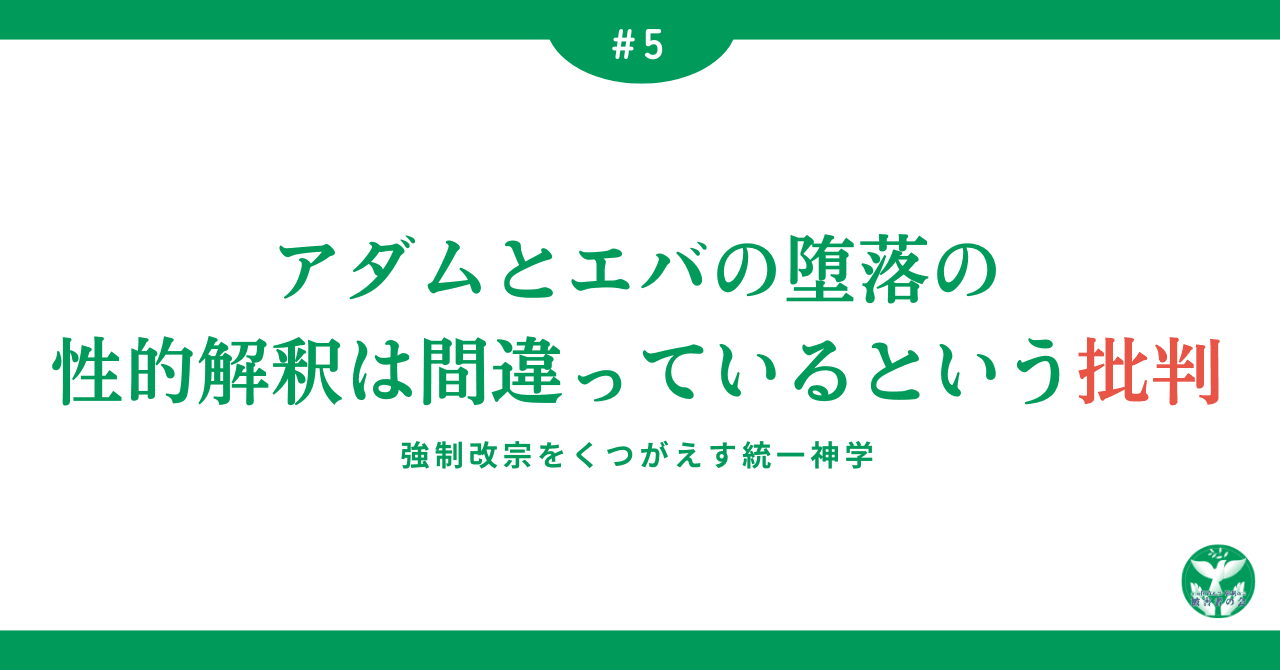
統一原理は、アダムとエバの堕落は、蛇に象徴された天使長ルーシェルを中心として不倫の愛の性的関係を持ったことにあると教える。
神の戒めで取って食べてはならないといわれた善悪を知る木の実は、文字通りの果実ではなく、エバの愛を象徴したものであると教える。
これに対して、福音派を初めとする既成のキリスト教は、堕落は、文字通り木の実を取って食べて神の戒めに背く不従順、高慢にあったと主張して、統一原理の性的解釈は間違っていると批判する。
しかし、既成のキリスト教の解釈は、歴史的に見るとアウグスティヌス (Augustinus) によって確立されたものであり、彼の絶大な影響力からして、以後のキリスト教の主流とはなったが、それが正しいという理由はどこにも無い。
その方が統一原理の立場に近い。
統一原理の性的解釈が、アウグスティヌスを中心とした既成のキリスト教の解釈と比べて、如何に整合性があり優れているかを以下に示そうと思う。
統一原理の性的解釈と既成キリスト教の性的解釈の比較と整合性
堕落に関する既成のキリスト教の解釈を確立したアウグスティヌスによると、堕落は個々人が行ったものであるという。
彼は、マニ教の宿命論に反対して、個人の自由意志による決定が鍵を握ることを説いた。
彼の『神の国』14巻13章によると、ルーシェルとエバとアダムはそれぞれ神から自由意志を与えられていて、それぞれ自分の自由意志によって神の戒めに背いて自分を高め、不従順、高慢になり、堕落することを選んだのであり、他者からの影響を受けて堕落したのではないという。
勿論、木の実を食べる行為をする時に、ルーシェルがエバを誘い、次にエバがアダムを誘ったという側面もあるが、それは既にそれぞれが自由意志で堕落してしまった後の結果であるに過ぎないという。
統一原理も、アダムとエバの堕落の中に不従順があったことは認めるが、それが個々人の自由意志から来たとは認めない。
『原理講論』によれば、自由意志は神から与えられたものなので、それは必ず原理と責任と善なる実績を伴うわけで、それによって堕落することはあり得ない。
人間の堕落は飽くまでも、自由意志がその志向する力よりも強い「非原理的な愛の力」の誘惑によって拘束されたところに起因するのである (125-127頁)。
このように、自由意志によって堕落したのではなく、かえって堕落によって自由意志を失ったのである。
だから統一原理は、堕落は、個々人の自由意志を行使する責任分担を果たそうとする矢先に、不倫の性的愛の関係が入り込んで横行したことにあるとして、個人的選択性よりも関係性の次元に重きを置く。
関係性の次元に注目する統一原理の性的解釈の方が、既成のキリスト教の解釈よりも聖書的である。
聖書の中でイエスが「あなたがたは自分の父、すなわち、悪魔から出てきた者であって、その父の欲望どおりを行おうと思っている」(ヨハネ伝8:44) といわれ、我々を「へびよ、まむしの子らよ」(マタイ伝23:33) と呼ばれたことからして、堕落してサタンになったルーシェルが我々の親であり、我々がその子供であるという血縁関係ができてしまったことが分かる。
これは、サタンとエバとアダムが不倫の愛の関係により罪の血統を作り、罪の子女たちを繁殖したという統一原理と一致する。
またイエスは、サタンを「この世の君」(ヨハネ伝12:31) と呼ばれたが、これも、アダム・エバの罪の家庭から、氏族、民族、国家、世界へと繁殖するに応じて、サタンの君臨する主権が拡大したという統一原理と一致する。
ところが、既成のキリスト教の解釈は、ルーシェルとエバとアダムの堕落をそれぞれに切り離して考えるので、サタン中心の血統関係とか主権とかいう概念が存在せず、イエスのいわれたことを説明できない。(ただし、キリスト教の歴史を見ると、サタンの主権という概念は、11世紀頃までは少し存在したことがあったが、その後はすっかり無くなってしまった。)
統一原理の性的解釈が既成キリスト教よりも優れているもう1つの理由
統一原理の性的解釈の方が既成のキリスト教の解釈よりも優れているもう一つの理由は、アダムの原罪が子孫に伝播されるメカニズムを矛盾なく説明できるということである。
アウグスティヌスは、原罪の伝播にコンクピスケンティア(情欲concupiscentia) の役割を考える。
彼によれば、このコンクピスケンティアは堕落の結果生じたものであり、堕落の原因ではない。
しかし堕落後は、いくら信仰的な親でも、生殖のために性的関係を結ぶ時には、このコンクピスケンティアから絶対に逃れられないから、性的関係を通して原罪が親から子供に伝播するという。
統一原理による堕落の性的解釈によれば、アダム・エバの堕落の瞬間からサタンを中心とした罪の血統が成立してしまっているので、このアウグスティヌスの理論は当然である。
しかし奇妙なことに、このアウグスティヌスの理論は、彼の初めの主張、すなわち、堕落は個々人の行いであり、性的関係ではなく、文字通り木の実を取って食べたことにあるという主張とはどうしても相容れない。
既成のキリスト教はこの矛盾に気が付かないか、あるいは気が付いたとしても説明しようともしない。
この矛盾の解決が無いので、近世以来、多くのキリスト教徒が、原罪はアダム個人の問題なのに、何故自分達がそれを背負わなければならないのか、と疑い始め、原罪の伝播を否定するようになり、混乱が生じている。
統一原理を知れば、このような混乱は起こらない。
最後に、興味ある話をひとつ。
それは、多くの聖書学者による理論であるが、創世記3章のアダムとエバの堕落に関する記述がなされた頃は、性的快楽、多産、不死などの目的で、蛇を神のように崇拝して性的不道徳を行ったカナン人の祭儀が広まった時代でもあったので、聖書記者はそれを批判する意図で書いたということである。
だからこの部分の聖書の記述は、アダムとエバの堕落は性的堕落にあったといいたかったとのことである。
神の絶対予定を否定しているという批判
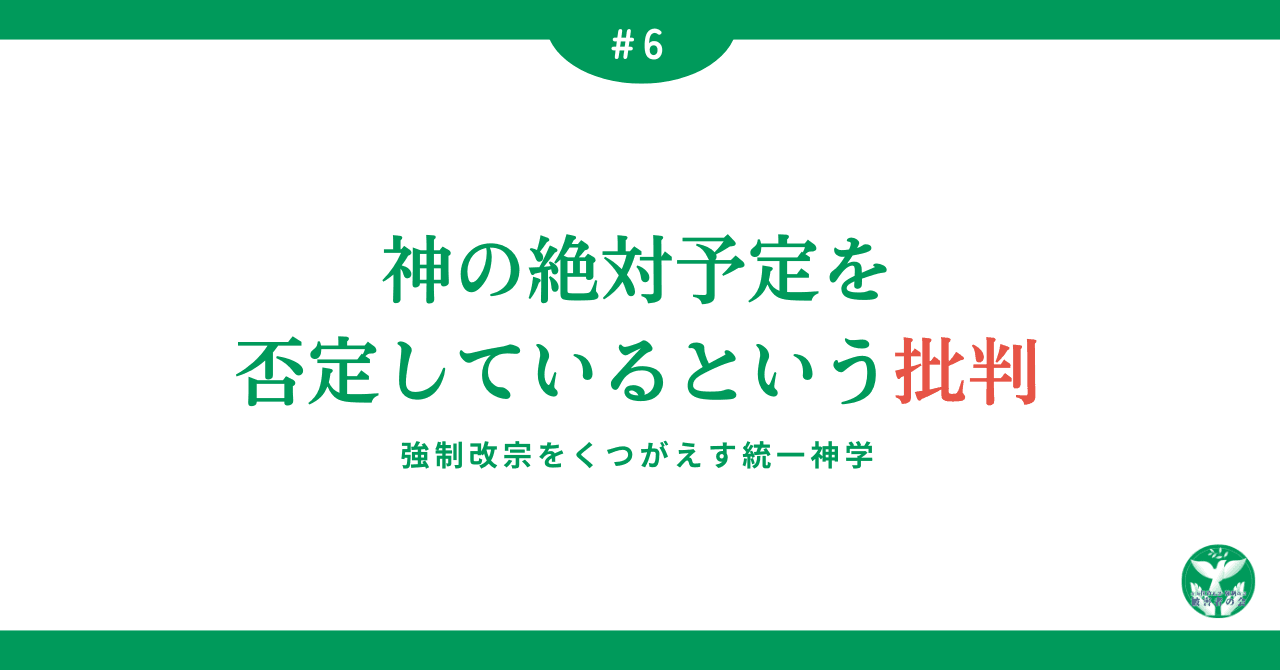
統一原理は、神のみ旨は、神の責任分担と人間の責任分担が共に果たされることによって成就される、と教える。
人間の責任分担もあるというのは、人間の努力も神のみ旨成就のために貢献するということである。
これに対して、カルヴァン主義の流れを汲む福音派は、神の予定は絶対であるために、この地上の出来事は全て神の予定によって定められているのであり、人間の努力は一切それに影響を及ぼさない、と主張する。
従って福音派は、統一原理は神の絶対予定を否定していると批判する。
これについて、カルヴァン主義は、神が絶対予定で以って悪をもたらすのは、我々の知らない神の大きな計画があってのことである、と説明する。
しかし、カルヴァン主義がそれを全ての悪に当てはめようとするのは、絶対予定を正当化するための詭弁に聞こえ、善なる神を冒涜するばかりか、歴史的に苦労して来られた神の愛の心情を蹂躙することにもなろう。
また、カルヴァン主義が人間の努力とか人間の責任分担とかを無視するのは、人間を神のロボットのように扱い、神の絶対予定ならば、善なることであろうが悪なることであろうが、全てをロボットのような人間にやらせることになる。
しかし、聖書をよく見れば、人間は決してロボットではなく、責任を持って神の摂理に参加することが期待されて来たことが分かる。
責任を持って神の摂理に参加することが期待された人間
旧約聖書によると、神は、期待を担ったイスラエル民族が摂理のために善なることをすれば喜ばれ、悪なることをすれば悲しまれたのではなかったか。
人間は本来「神のかたち」に造られた (創世記1:27)。
これは、統一原理によれば、人間が創造の神に似て創造性を与えられたことを意味する。
だから人間は、その創造的努力から来る責任分担を遂行して神のみ旨成就に貢献し、神を喜ばせることになっている。
そして堕落後も、人間の責任分担を遂行しながら救いの過程を通って行くのである。
実は、キリスト教を見れば、神の絶対予定と共に人間の努力をも考慮するアルミニウス主義の立場があることが分かる。
このアルミニウス主義は16世紀と17世紀初頭に活躍したオランダ改革派の神学者アルミニウス (Jacobus Arminius) の考えから来たもので、カルヴァン主義者たちからひどい批判と迫害を受けたが、後ほどメソジスト教会やホーリネス系の教会などの神学に流れ込み、キリスト教の中で異端視されずに存在している。
カトリック内にも、アルミニウス主義に似た学派が16世紀にあった。
イエズス会の神学者モリナ (Luis de Molina) によるモリナ主義であり、この学派は、神からの「援助に関する 」(De Auxiliis) 論争で、 カルヴァン主義的なドミニコ会の神学者バネズ (Domingo Báñez) 側から迫害を受けたが、最終的には1607年にローマ法王から異端ではないと公認された。
だから、統一原理が神の責任分担と共に人間の責任分担について語る時、福音派は、統一原理が異端であるなどとは絶対にいえない。
ただ、統一原理とアルミニウス主義が神学的に全く同じであるというのではない。
神の予定と人間の努力を調和させる方法論において、統一原理とアルミニウス主義は互いに異なる。
統一原理とアルミニウス主義の相異点
先ず、アルミニウス主義によれば、神の予定と人間の努力は神の予知というものによって調和させることができるという。
神は、人間がこれから自分の自由意志によって如何なる決定をし如何なる行動をするか、を前もって予知されているので、ご自身のその予知に基づいて、人間がこれから自由意志でするであろう全てのことを予定されるというのである。
神の予知によるこの調和の方法は、いささか言い訳のように聞こえないでもない。
次に、統一原理による神の予定と人間の努力の調和法を見てみよう。
『原理講論』によれば、神のみ旨に対する予定は、神が絶対者であられるゆえに、絶対である (240-242頁)。従って、人間の努力が不十分でみ旨が成就されない場合でも、神は他の人間を立てて努力をさせて、最終的にはみ旨を成就させなければならない。
結局これは、み旨に対する予定は絶対的であるが、み旨成就に対する予定は相対的であるということを意味する (243-244頁)。
これは、み旨に対する予定が絶対なのに、その成就が延長されて来たという歴史的現実をよく説明し、聖書に記録されている神と人間の関係をよく言い当てている。
「カルヴァン主義の五特質」(TULIP) に反しているという批判
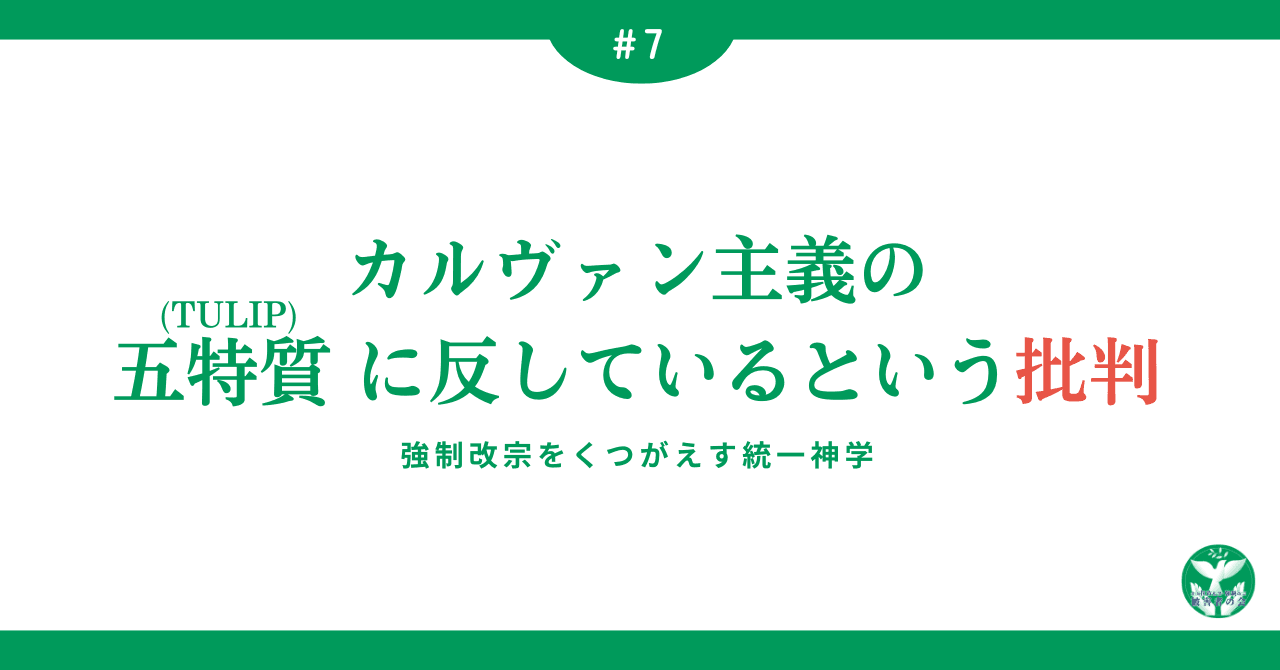
カルヴァン主義の流れを汲む福音派は「カルヴァン主義の五特質」なるものを以って統一原理を測り、統一原理はそれに反していると批判する。
「カルヴァン主義の五特質」は、1618-1619年にオランダ改革派教会によって開催されたドルトレヒト会議で「ドルト信仰基準」として確立されたもので、カルヴァン主義の救済に関する五つの主要特質を表している。
それは、「全的堕落」(Total Depravity)、「無条件的選び」(Unconditional Election)、「限定的贖罪」(Limited Atonement)、「不可抗的恩寵」(Irresistible Grace)、「聖徒の堅忍」(Perseverance of the Saints) である。
英語の言葉の頭文字を取るとTULIP (チューリップ) となるが、これは英語圏での順序であり、元々の順序とは違う。
五特質の内容を簡単に説明すると以下のようになる。
これを見ると、如何にカルヴァン主義が神の絶大なる主権と力を強調しているかが分かる。
堕落した人間が無力であり、神の主権と力は絶大であるのは当然であるが、カルヴァン主義はそれを強調するが余りに、不幸にして、救われる人間と滅ぼされる人間を初めから決定してしまう無慈悲な神を作り上げてしまった。
しかし、神の本質は全ての人を救わんとする愛ではなかろうか。
だから聖書も、キリストによる贖罪が「わたしたちの罪のためばかりではなく、全世界の罪のためである」(1ヨハネ書2:2) といって、万民への神の愛を紹介している。
カルヴァン主義の主管性転倒の間違い
カルヴァン主義は、神の絶大なる主権の名の下に、神の本質を歪めてしまって、結果としては、人間側が神を主管するという主管性転倒の間違いを犯している。
即ち、皮肉にも、神の主権の名の下に神の主権を無視している。
このような皮肉な例はまたとあるまい。
勿論、カルヴァン主義者たちは神の愛を告白する。
しかし、彼らは神の力を先ず前面に出して神の愛を後回しにするので、上述のような歪められた神学が出て来る。
かえって逆の順序で、先ず神の愛を前面に出して、その次に、万民に対するその神の愛を実現させるためには、神はどのようにしてご自分の主権と力を発揮されるのか、と論じた方が健全な神学が出て来るのではなかろうか。
このような提案は、アルミニウス主義の伝統を相続するメソジスト教会の人たちからもよく出されるが、統一原理も賛成である。
実は、「カルヴァン主義の五特質」が1618-1619年に確立される以前に、オランダ改革派教会内でカルヴァンの絶対予定説に疑問を持ったアルミニウスを祖とするアルミニウス主義者たちが、五項目の信条を採択した。
それは、アルミニウスの死の直後の1610年であった。
その五項目の信条の中には、条件的選び、限定されない贖罪、可抗的恩寵などが含まれていた。
アルミニウス主義者たちとしては、カルヴァン主義が聖書とはかけ離れた神観を持っているといいたかったのである。
しかし「カルヴァン主義の五特質」は、正式にそれを蹴って退けたわけである。
問題なのは、その直後、アルミニウス主義の支持者であった有力な政治家オルデンバルネヴェルト (Johan van Oldenbarnevelt) が無慈悲にも死刑にさせられ、当時の200名ぐらいの全てのアルミニウス主義の牧師も異端として職を追われたことである。
この無慈悲な仕打ちも、神の愛を後回しにして神の絶大なる力を誇示すればこそ可能だったのであろう。
統一原理 神の真の愛
統一原理は、神の真の愛を強調する。
全ての人間が神の愛する子女であるがために、神は、人間全てが救われるのを願われる。
それを心の底から知り尽くされた文鮮明師は、神を否定した共産主義者にも神の絶大なる愛を伝えるために、1990年代の初めにソ連と北朝鮮を訪問してその首脳と会談された。
師の『自叙伝』によると、師は少年時代の頃から、ご飯を食べる時、貧しくて食えない人のことを思うと「胸が痛く、喉が詰まって、スプーンを持つ手が止まってしま」ったそうである (22頁)。それが神の真の愛ではなかろうか。
人類歴史を通して、真の愛の神は、たとえ人間が裏切って反逆しても、再び決意して忍耐し愛し続けて来られた。人間が最終的に神に帰って来るようにするためである。
実は、神の力は、この忍耐と愛の中にこそにじみ出るのであって、誰もその力をくい止めることはできない。
その意味でこそ神の力は全能である、と統一原理は見る。
人間を神扱いしイエスを人間扱いする傲慢で冒涜的なキリスト論だという批判
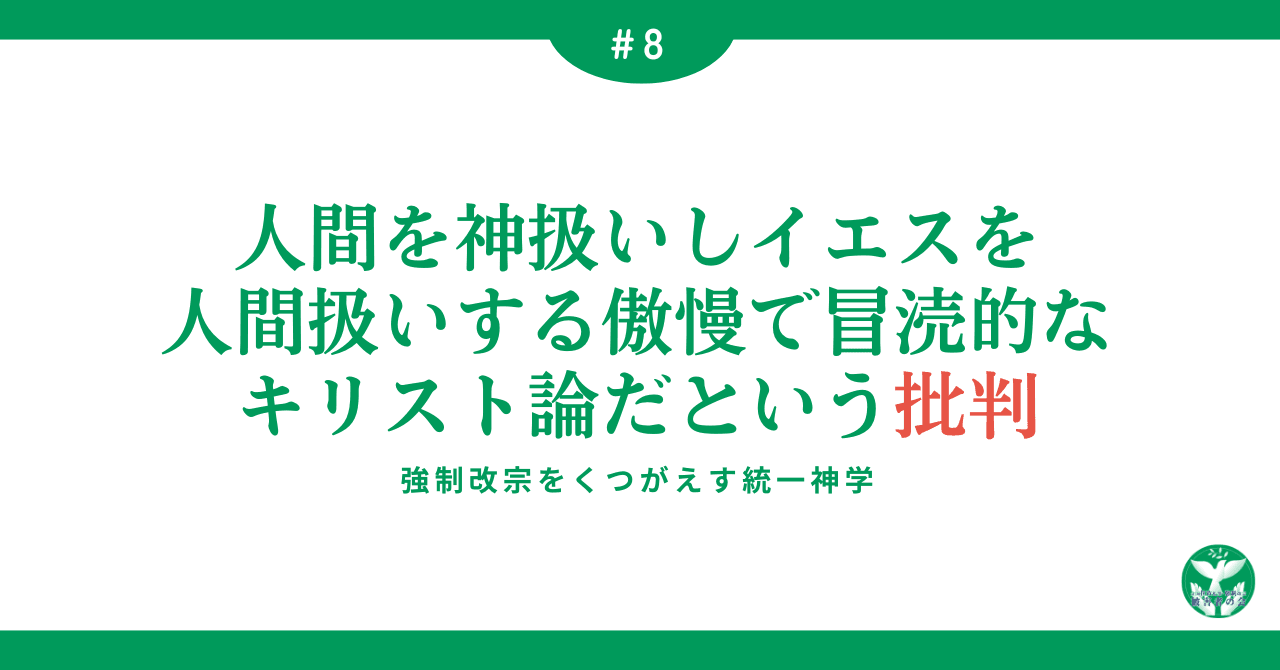
『原理講論』のキリスト論は、創造目的を完成した人間は、神と完全一体化して神性を帯び神のような価値を持つと説く一方で (252頁)、イエスは神ご自身ではなく、正にこのような創造目的を完成した人間であられると主張する (256-257頁)。
これは、創造目的を完成した人間の価値を神やイエスの価値と同等の立場に引き上げるだけであって、イエスの価値を決して少しも下げるものではない (257頁)。
人間を神扱いすることが傲慢であり罪という批判
先ず、人間を神扱いすること自体が傲慢であり罪であるという批判に応えれば、ギリシャ語圏の東方キリスト教会では初めから、人間の救いの目的は、神のようになって神性を帯びる「神化」(theosis) にあると考えられていたことを知って欲しい。
エイレナイオス (Irenaeus)、ヒッポリュトス (Hippolytus)、アタナシウス (Athanasius)、ニュッサのグレゴリオス (Gregorius Nyssenus)、ナジアンゾスのグレゴリオス (Gregorius Nazianzenus) などのそうそうたる教父たちが、イエス降臨による人間の救いに関して「神が人となったのは、人が神となるためであった」という意見であった。
人が神そのものになるというのではなく、神のようになるということである。
そして、西方教会のアウグスティヌスまでもこれに同意していたといわれる。
だから、統一原理が、人間が完成して神性を帯び神のような価値を持つという時、キリスト教の初期の教父たちの考えと軌を一にしているのであり、決して傲慢な見解ではない。
聖書も、我々が「神の性質にあずかる者となる」と述べているではないか (2ペテロ1:4) 。
イエスを人間扱いし冒涜しているという批判
次に、統一原理がイエスを人間扱いし冒涜している、という批判に応えよう。
逆に、このような批判をする福音派を初めとする既成のキリスト教こそ問題であることを知るべきである。
確かに聖書には、イエスが神性を帯びた方であることを示す聖句は多くあるが、それは、イエスが神ご自身であるという証拠には決してならない。
イエスも自分が神ご自身であるとは決していわれなかった。
しかしニケア公会議は、イエスの神性を否定したアリウス (Arius) を異端として退ける目的のために、イエスは父なる神と「同質」なる (homoousios) 神の子として、神によって創造されたのではなく、「真の神」から出た「真の神」であると決定してしまった。
勿論、451年のカルケドン公会議においては、当時のキリスト教指導者たちは、イエスは「真の神」 (vere Deus) だけでなく「真の人間」 (vere homo) でもあるということは認めた。
しかし、その後が問題であった。
イエスは飽くまでもお一人の方でしかあられないので、イエスの位格に関して、結局は真の神と真の人間のどちらかを選なければならなかった。
結局は当然、真の神の方を選び、イエスの人間としての人性 (人間性) を中途半端な「位格を持たない性質」(physis anhypostatos) として見下し、イエスが真の人間であることをすこぶる軽視してしまったのである。
このような歴史的経緯で、イエスは人間ではなく人間の姿をした神ご自身であるという見解が定着したのである。
後世の学者たちは、これを「上からのキリスト論」と呼んだ。
神と同一視されたイエスが、上から下の人間の次元に下って中途半端な人性を帯びる、というキリスト論だからである。
上からのキリスト論
この伝統的な「上からのキリスト論」は、明らかに、イエスが「真の人間」でもあるというカルケドン公会議の決定に反している。
それはまた、イエスを実に人間らしく描く聖書にも反している。
統一原理のキリスト論は「上からのキリスト論」ではない。
統一原理は、カルケドン公会議が元々いいたかったこと、即ち、イエスが「真の神」であるだけでなく「真の人間」であるということを、上手に説明できる独自の方法を持つ。
先ず、イエスが創造目的を完成した人間として、真の人間であられることは明白だ。
次に、イエスは創造目的を完成した人間として神ご自身ではないが、神と完全一体化しているので、神性を完全に受け継ぎ、神のような価値を持っているという意味で、真の神の立場であられる。
だから統一原理のキリスト論は、イエスの神性を否定した人間的なアリウスのキリスト論でもない。
実は、宗教改革を行ったルターも統一原理のように、伝統的な「上からのキリスト論」や異端のアリウスのキリスト論とは無関係であった。
ルターは、純粋に聖書的な見地から、イエスは上述の「位格を持たない性質」として見下された人性しか持たない生半可な人間などではなく、地上の史的イエスとして具体的な位格を持った真の人間として、真の神と一体化していると直観して、それまでとは違ったキリスト論を提示した。
ただ、ルターは、真の人間と真の神の完全一体化について述べても、それが如何にしてできるのかをよく説明したわけではなかった。
統一原理によれば、神人一体化は、神の二性性相が人間の中に実体対象化して、人間が神の二性性相に完全に似るようになった時に実現する。
詳細は省くが、この二性性相が神の内部 (本性相と本形状の二性性相) だけでなく人間の内部 (心と体の二性性相) においても授受作用によって完全一体化するようになった時に、神と人間の縦的関係においても両者が完全一体化する。
統一原理のいう神の二性性相の概念に似たような考えは、ルターの神学の時から少しずつ出現し始め、その伝統を受け継いだ20世紀のバルトやモルトマンの神学にも見られ、そして、アメリカのプロセス神学などにはっきりと現れて来た。
これらの神学は、その二性性相によって神と被造世界の緊密な関係を説明しようとした。
従って、イエスが創造目的を完成した人間として神と完全一体化している存在であられる、と主張する統一原理のキリスト論が世界に認められる神学的下地は着々と準備されている。
統一原理から見た神の人間創造目的について一言
最後に、統一原理から見た神の人間創造目的について一言。
『原理講論』によれば、神の二性性相が人間の中に実体対象化して、人間が神の二性性相に完全に似るようになれば、神がその人間から来る刺激によって、ご自分の二性性相を相対的に感じて喜ぶことができるようになるが、創造目的とは、正にこの喜びを神も人間も体験することなのである (65-66頁)。
だから、創造目的である喜びの体験が起こるためには、創造目的を完成した人間は、確かに神の喜びの対象として完全に神性を帯びてはいるが、神そのものではなく神とは異なる対象物でなければならない。
もし万が一、イエスが神ご自身であったならば、神がイエスをご覧になって喜ばれることは不可能なのである。
筆者は、洋の東西を問わず、今まで出版された組織神学の本を無数に読んだが、どの本も創造目的に関してはスペースを少ししか割かず、ひどいのになるとスペースが全然無く、しかも創造目的の説明が曖昧で自信がないものばかりであった。
正直いって、絶対なる神が何の目的で被造物を創造しなければならなかったのかは分からない、と告白する組織神学の本が実に多かった。
神の創造目的を知らない福音派を初めとする既成のキリスト教は、イエスがどのような方であられるのかについて論ずるキリスト論なるものを構築する資格はない。
神がイエスの一挙手一投足をご覧になって喜ぼうとされたこと、また、イエスが周りから反対された光景をご覧になって神が心を痛められたことなどを知るべきなのに、残念ながら、既成のキリスト論は、全然それを知ることができないでいるのである。
自力信仰であるという批判
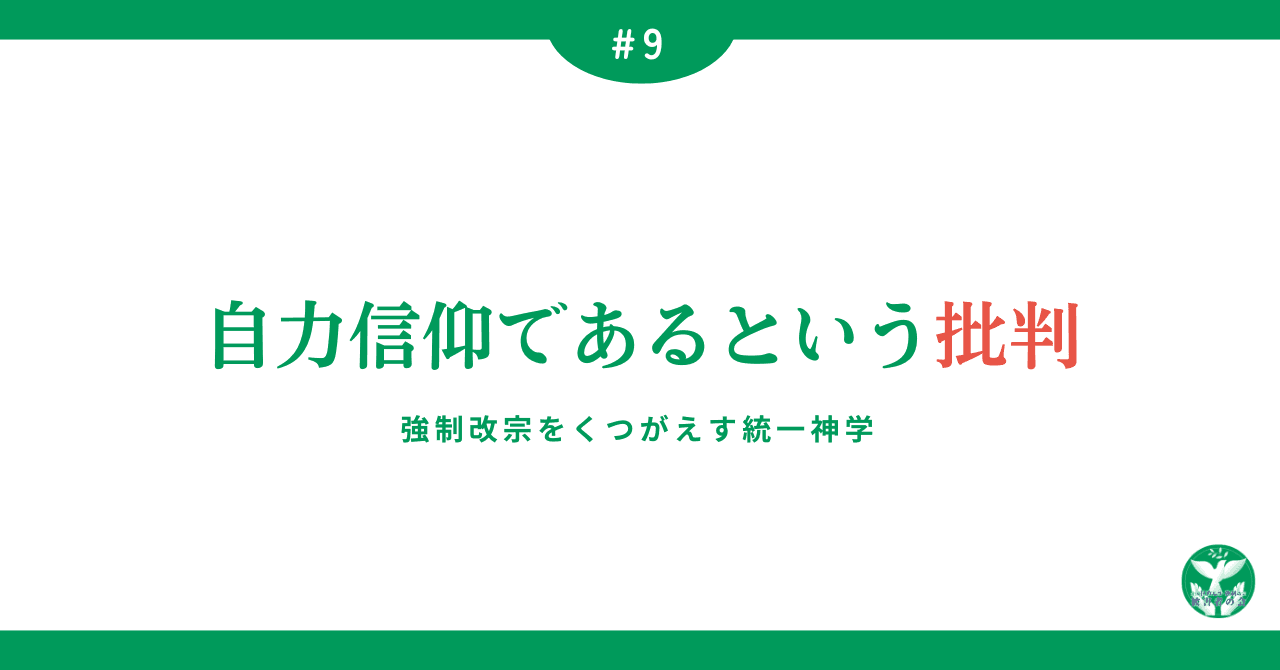
統一原理は復帰原理において「蕩減復帰」について語り、人間は何らかの蕩減条件を立てることによって復帰されると教える。
これに対して福音派は、救いには条件など不必要であり、ただ信じれば無条件で救われると主張し、統一原理は自力信仰を教えていると批判する。
しかし福音派は、人間の救いの全過程を見ることなく、その一部だけを見て、それが全てだと思う間違いを犯している。
確かに、堕落人間は、最初は霊的に余りにも幼く神から遠いので、独りでは何もできない。
それで、人間の救いは神の一方的な愛によって決められ開始されたと考えられる。
しかし、それが全てではない。
救いの過程において次第に成長すれば、人間も何らかの責任を果たすことによって、神が願われる救いの完成に向かうようになっている。
アウグスティヌスによる救いの過程2段階
だからアウグスティヌスも、その著『恩寵と自由意志』の33章において、救いの過程を大きく二段階に分けて、
神と人間が協力するという第二段階を聖書からサポートするために、アウグスティヌスは「神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて」(ローマ書8:28) という聖句を引用する。
アウグスティヌスは、カトリックは勿論のことプロテスタントのルターやカルヴァンにも大きな影響を与えた神学者であるが、カトリックは彼のこの理論の中での第二段階を主に採用し、プロテスタントは第一段階のみを採用したといわれている。
しかし、アウグスティヌスの理論の全体像を見るべきであり、特にプロテスタントの福音派などのように、第一段階だけにしがみ付いて、狭い分野で、ただ信じれば無条件で救われると主張し続けるのはよくない。
ヤコブ書2:24 も「人が義とされるのは、行いによるのであって、信仰だけによるのではない」と述べているではないか。
アウグスティヌスの理論での第二段階は、第一段階を一旦通過しているので、そこで成長した自由意志によって責任を持って条件を立てても、それは自力信仰ではない。
しかも、その自由意志の背後には神の「協力的恩寵」が共にあるのである。
統一原理の”復帰のための蕩減条件”の教え
同じように、統一原理が、復帰のための蕩減条件を立てることを教えていても、長い復帰の過程を通過するのが前提になっているし、また、背後に神の責任分担が共にあるので、それは自力信仰を薦めているのではない。
統一原理によれば、堕落人間の復帰の過程は、全く自由の無い僕の僕の段階から始まって、僕の段階、養子の段階、庶子の段階などを通過して、神の実子の段階に到達して神に戻って行く過程である。
そして、この過程を通して次第に責任性と創造性のある人間に成長して行くのである。
このように獲得された責任性と創造性からは、神と衝突するような自力が生じないのが原則である。
かえって、救いの過程の当初の段階だけにしがみ付いて狭い分野で信仰生活をする福音派の方が、神の全体的摂理過程を無視して、皮肉にも、神に反する自力信仰のような間違いを犯す結果になってしまっているのではなかろうか。
また福音派は、信仰のみによって無条件で救われるというが、信仰を持つことが救いの条件にもなっていることに気付くべきであろう。
12年間も長血をわずらった女が信仰で以ってイエスの衣を触り自分の病気が治ったので、イエスは「あなたの信仰があなたを救ったのです」(マタイ伝9:22、マルコ伝5:34) といわれた。
また、聖書は、このような人間の信仰は神を喜ばす条件になるといっている (ヘブル書11:6)。
統一原理も、信仰者が復帰のために信仰条件を立てる必要性を説き、それを「信仰基台」と呼ぶ。
ただ、エペソ書2:8などには、信仰は人間から出たものではなく神の賜物である、と書いてあるので、福音派などは、信仰は人間が立てる条件であるはずはなく、人間はやはり無条件で救われると主張し続けるが、このような聖句は飽くまでも、救いの過程の一番初めの段階で人間が極めて無力であることを強調するためのものであったと取れるであろう。
十字架贖罪を否定しているという批判
統一原理は、イエスの十字架上の死は神が予定されたものではなく、イスラエル選民の不信仰の結果生じたものであり、本来イエスは地上に生き長らえて神主権の天国を造成されるはずであった、と教える。
そして十字架によってもたらされたのは霊的救いのみであったと説く。
これに対して、福音派を初めとする既成のキリスト教は、イエスの十字架は神の予定であり、それによる贖罪は絶対的なものであるので、統一教会は十字架贖罪の絶対性を否定する大きな間違いを犯している、と批判する。
しかし、20世紀には実に多くの神学者が、統一教会と同じように、イエスの十字架上の死について反省しながら、それが決して神の予定ではなく、不幸な出来事であったと主張し始めるようになったので、それについて簡単に紹介してみたい。
20世紀の神学者によるイエスの十字架に対する新しい考え
先ず、ドイツのカトリック神学者ロマーノ・グァルディニ (Romano Guardini) は、イエスが十字架の死に追いやられた結果、神の国は到来せず、アダムの罪は消えず、人間は「第二の堕落」を経験することになったと主張した。
ドイツの新約聖書学者ヴィリ・マルクセン (Willi Marxsen) は、イエスご自身が、十字架で死なずに生き長らえて地上天国を実現しようとされたと説いた。
スイスのカトリック神学者ハンス・キュング (Hans Küng) は、イエスに敵対する強力な勢力ゆえにイエスは十字架で殺され、その結果、神の国の速やかな到来はなかったと述べた。
アメリカのメノナイト派の神学者デニー・ウィーヴァー (J. Denny Weaver) は2001年に出版した『非暴力的贖罪』(The Nonviolent Atonement) の中で、イエス降臨の本来の目的は十字架で死ぬことではなく、地上でサタン主権を神主権に変える戦いをするためであったと説いた。
アメリカの元カトリック司祭ジェームス・キャロル (James Carroll) は2002年に出版した『コンスタンティヌスの刀』(Constantine’s Sword) の中で、人間の救いは十字架によるのではなく、イエスの生涯全体によるのであり、十字架がキリスト教のシンボルとして使用されたのはコンスタンティヌス大帝 (Constantinus) からのことであり、それ以前は魚がシンボルであったと説明し、更には、十字架を強調すると、残念ながらキリスト教徒はユダヤ教徒を必要以上に排斥するようになると論じた。
1960年代以降の十字架の否定的な見解
このような十字架に対する新しい考えは、多かれ少なかれ、聖書批評学の影響もあって出て来たと考えられるが、1960年代以降は、聖書批評学とは無関係に、十字架に否定的な見解が独自に、黒人解放神学や女性解放神学などから出現してきた。
それによると、十字架は、黒人や女性や弱い者たちを力で屈従させるために使う抑圧の道具のようになってしまい、人間の救いや解放には役立たない、というのである。
十字架の屈従の道はイエスが行かれたのだから、お前たちも当然その道を行けという論法で、教会の権力者は自分たちが行くべき屈従の道をそっちのけにして、弱者をやたらと抑圧して来るというのである。
そして、愛の神がその独り子を十字架で殺すような、いわゆる児童虐待によって人間の贖罪をされるなどとは考えられない、と主張する。
福音派としては、このように20世紀に出現した新しい見解は全部リベラル派から来たものであろうから取るに足らない、というかも知れない。
しかし、キリスト教の歴史を見ると、十字架贖罪が神の予定された絶対的なものであるという見解は、決して当初からあったものではなく、11世紀のカトリック神学者アンセルムスが確立した「充足説」の贖罪論から始まったものに過ぎないということが分かる。
この「充足説」は、16世紀にはプロテスタントの中にも「刑罰代償説」という新しい名前で浸透し、キリスト教の主流となってしまい現在に至っている。
「充足説」出現前は「古典説」が主流だった
ここで我々が注目すべきは、「充足説」出現の11世紀以前は、十字架をさほど強調しない「古典説」の立場が教会の主流であったことである。
この「古典説」は残念ながら11世紀以降は忘れ去られ、16世紀のルターによって一時的に再発見されたが、またすぐに忘れ去られ、再び注目をあびるようになるのは、1931年にスウェーデンのルター派教会の神学者グスターフ・アウレン (Gustaf Aulén) が、その名著『勝利者キリスト』(原題 Christus Victor、日本語訳、教文館1982年出版) を出版し、「古典説」の正当性を世に問いかけた時からである。
現在では多くの信仰者が再び「古典説」を支持するようになって来て、十字架の意味についての新しい問いかけがなされている。
それゆえ、福音派が「充足説」や「刑罰代償説」のみに則り、イエスの十字架を神の絶対予定であるかの如く振りかざす時代は長くは続かないであろう。
カトリックの「充足説」とプロテスタントの「刑罰代償説」は、堕落によって生じた神の怒りを宥め神を満足させるためには、イエスが堕落人間の代理として死ぬしかないと断じて、イエスの十字架は神の絶対予定であったとする。
確かにイエスは最終的には十字架で死なれたが、その死はイエスの生涯中に沢山ある出来事の中の一つに過ぎないのであり、決して神から絶対的に予定された最も重要な出来事ではなかったとする。
統一原理も「古典説」と同じように、イエスの生涯中の全ての出来事が、サタン主権を打倒して神主権の天国を造成するためにあったと見る。
しかし、当時のイエスを取り巻くイスラエルの環境は余りにもサタン的であり、ユダヤ教指導者は神の本来の願いに反してサタンを中心にローマ帝国と結託して、イエスを十字架で殺害してしまったのである。
『原理講論』と「古典説」解釈の一致
統一原理によれば、このようなイエスの悲惨な死は、サタン主権を少なくとも霊的な次元で打倒し、霊的な救いをもたらしたと説く。
『原理講論』によれば、「サタンがその最大の実権行使をもって、イエスを殺害したことに対する蕩減条件として、神もまた、その最大の実権を行使されて、死んだイエスを復活させ、すべての人類を復活したイエスに接がせ、彼等を重生させることによって 救いを受けられるようにされた」とある (423頁)。
これは「古典説」の解釈と同じである。
「古典説」と一つ違う点といえば、統一原理は飽くまでもこれを「霊的救いのみ」(187、425頁) と見なすので、完全な救いと贖罪をもたらすために、イエスの再臨の必要性をより強く説くことである。
このようにキリスト教全体を見れば、今まで主流の贖罪観だと思われて来た福音派を中心とした既成のキリスト教の十字架贖罪観は、初めから主流ではなかったし、また20世紀になってキリスト教の各方面から批判され始めていることが分かる。
従って、統一教会をこの件で批判するのは不当である。
真のご家庭に対する批判
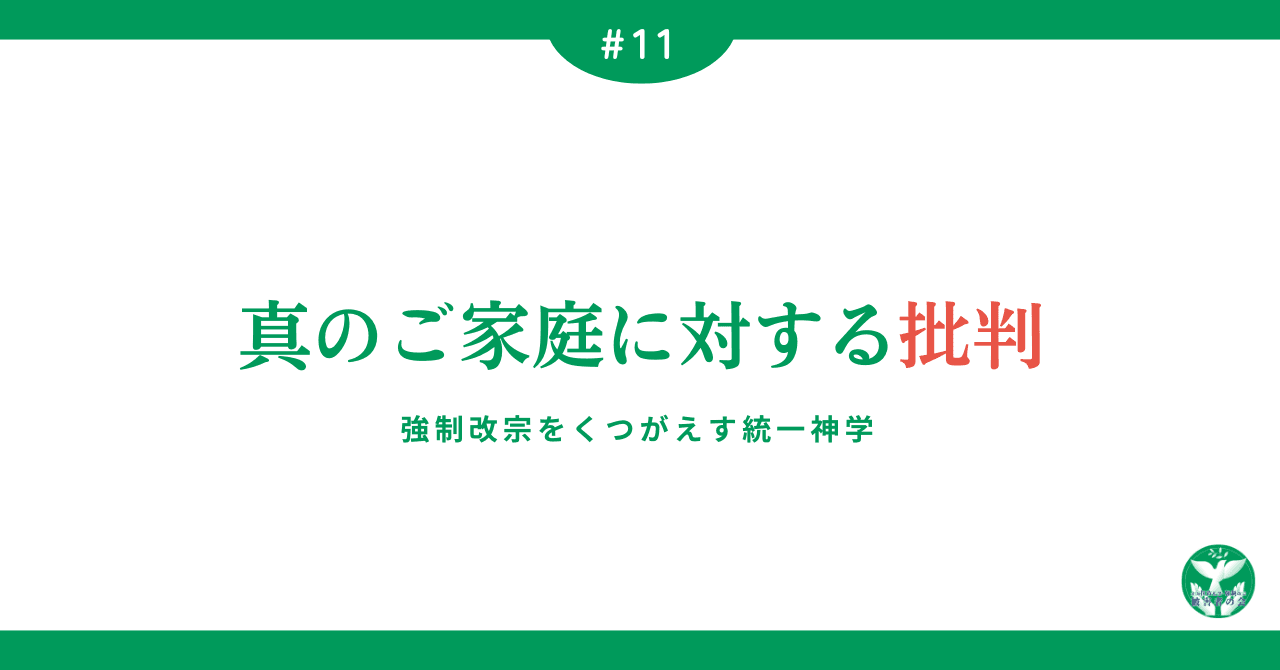
多くの反対牧師たちは、真のご子女様の問題、特に孝進様の問題を取り上げて、真のご家庭を批判し、真のご家庭の価値を否定しようとしている。
それに対してコメントをしてみようと思う。
筆者はアメリカ在住の日本人として長年の間、孝進様とは個人的な交流があった。
1975年のある日、筆者が教会の館のある部屋の中で独り感傷に浸りながらクラシック・ギターで叙情的な調を弾いていた時、突然その部屋に、13歳の腕白盛りの孝進様が大声で友人と追いかけっこをしながら走り込んで来られた。
しかし、ギターのメロディーを耳にされた途端、孝進様は筆者の直ぐ前に座り込み、しんみりと聴かれたのである。
曲が終ったら、もう一曲アンコールされ、筆者の腕前がそんなによくないのに、それにもジーッと耳を傾けられた。
さきほどの腕白ぶりはどこに行ったのやら。
その時、孝進様が如何に芸術的な美に敏感であられるかを知った。
そのお悩みとは、真のご父母様の実子として、周りから真のご父母様と同じ基準を要求されるプレシャーが余りにも大きいことであった。
周りの人たちが未だに大したこともない人間であっても、要求して来る目つきだけは鋭いので、それが耐え難いのだとおっしゃった。
筆者としては、ただ静かに忍耐して行かれるしかないと応えるだけだったが、真心を込めて応えたせいか、孝進様は「今日は実にいいことをきいた」と嬉しそうであられた。
その後、統一神学校で筆者の担当する神学の講義も聴講されたが、その時の孝進様の感想文は、未だに未熟な筆者から見ても、宇宙の真理に対する驚くべき神学的洞察と直観が散りばめられたものであった。
このように、筆者の体験によれば、孝進様は素晴らしい感受性と能力を持つ人間であられたことは間違い無い。
しかしながら、初めから神と一体化した完成人間である者は誰もいないことも確かである。
孝進様も例外ではない。
孝進様の問題の2つの理由
孝進様の問題には二つの理由があったと考えられる。
一つは、一寸前に述べたように、周りにいる我々が未だに大したこともない人間なのに、孝進様に対して、真のご父母様と同じ基準を要求する大きなプレシャーを与えたからである。
単なるプレシャーだけだったら、孝進様もはねのけることができたと考えられるが、問題は我々が、真のご父母様の偉大さを他人事のように外的な知識としては知っていても、その内容を自分の実存の中に内的に実現して実感するところまで行かなかったということである。
このような不足な状態では、真のご子女様を支えることはできないだろうし、ましてや、真のご父母様を支えることはできない。
不足な12弟子たちもイエスを支えることができず、サタンの侵入を許し、イエスを十字架の死に追いやったのではないか。
我々も同じような形で真のご家庭を十字架に追いやったのではなかろうか。
これは、我々が謙虚に反省して、一刻も早く解決すべき問題である。
第二の理由は、如何なる人間も初めから完全な人間ではないからである。
孝進様も例外ではなく、イエス様や真のご父母様といえども例外ではなかった。
2世紀の神学者エイレナイオスによれば、アダムは未熟な人間として造られて、一定の成長期間を通過することになっていたという。
そして、イエスも「後のアダム」として、アダムの成長の道を踏襲してキリストになられるという理論を提示した。
アウグスティヌスによれば、堕落する前のアダムは「罪を犯すことができない能力」(non posse peccare) ではなく「罪を犯さない能力」(posse non peccare) しか持っていなかったので、初めから完全人間ではなかったことになる。
統一原理は、人間は成長期間中に責任分担を果たすことによってのみ完成して行くと説く。
だから、罪がなくても未だ不完全だったアダムは途中で罪を犯す可能性があったし、実際は堕落してしまったのである。
その可能性は誰にでもある。
厳密には、祝福家庭といえども未だ完成圏に入っていない限り、同じ間違いを起こす可能性はある。
いずれにせよ、完成圏に入っていらっしゃる真のご父母様に感謝しつつ、我々もその内容を自分の実存の中に内的に実現して実感できるようになるために努力するしかない。完成圏にいらっしゃる真のご父母様を批判することは絶対に誰もできない。
社会問題を引き起こす悪なる団体だという批判
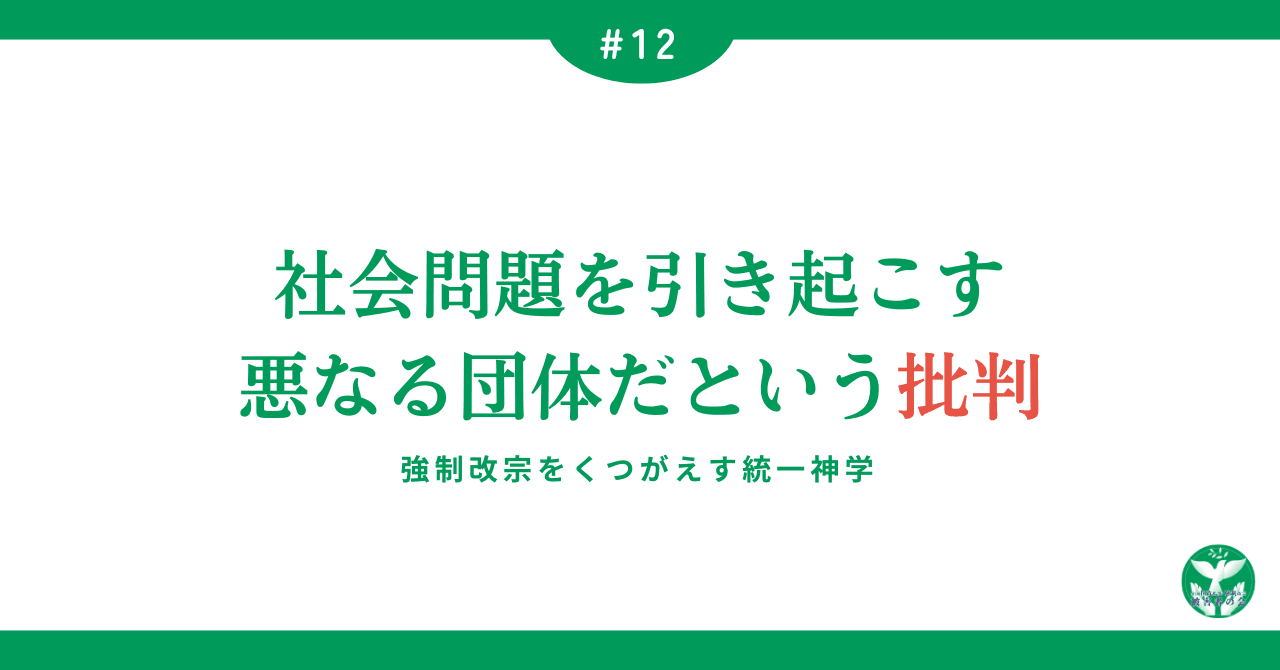
多くの反対牧師たちは、統一教会が多くの社会問題を引き起こす悪なる団体だと決め付けて批判する。
しかし如何なる宗教も、何らかの新しいインスピレーションを持って出発する限り、現実社会とその一部である既成宗教へのある意味での挑戦となるので、一般的に反社会というレッテルを貼られて迫害されるのは避けられないようである。
2000年前にメシアとして出現されたイエスの新しい教えも、イスラエル社会とユダヤ教にとっては大きな脅威となり、反社会的なもの、更には悪魔から来たものと見なされて批判された。
だから再臨の摂理を担う統一教会が誤解され迫害されるのも当然の現象であろう。
一旦誤解されれば、統一教会が如何に素晴らしい社会奉仕、平和運動、芸術プロジェクト、伝道活動、経済活動といった活動をしても、批判され続ける。
統一教会側が、そのような批判に対処するために何らかの具体的な手を打っても、それもまた違法だとか反社会的だとかいわれて事態は一層悪化する。
勿論、統一教会が未だ完全であるはずはないし、様々な批判に対処する時のやり方が未熟だったりして、より一層の誤解を招いたことは事実である。
しかし統一原理の理念からすれば、特にその神観からすれば、統一教会は、絶対に人間を悪い方向に陥れる悪なる団体であるはずはない。
文鮮明師が発見された神の愛は、堕落によって失われた万民が一人残らず帰って来るまで心が休まらず、涙を流して苦労される神の真の愛なのである。
それは怨讐までも愛し、最終的にはサタンまでも救わなければならないとする神の愛なのである。
統一教会の全ての活動や事業は、このような神の愛が原点となっているのである。
イエスも説かれた神の愛
2000年前のイエスもこれと全く同じ神の愛を説かれたことは明白である。
イエスが哀れな取税人や罪人たちと一緒に食事をされた時、パリサイ人や律法学者たちは、そんな下賎な人たちと何故交流するのかといわんばかりに、それを批判したが、その時イエスは彼等に向かって、一匹の失われた羊を捜し求める譬え話 (ルカ伝15:4-7)、一枚の失われた銀貨を捜す譬え話 (ルカ伝15:8-10)、帰って来た放蕩息子の譬え話 (ルカ伝15:11-32) などをお話になった。
全ての人に漏れなく愛を施される神の愛が、ここに如実に表現されている。
しかし、既成のキリスト教は、イエスの真の愛の教えに反して、救われる者と救われない者の二つのグループを無慈悲にも分けてしまい、自分だけが救われればいいのであって、救われない者は永遠に地獄に行ってしまえ、といわんばかりの神学を勝手に作ってしまった。
これこそ大きな罪である。
これは、神の絶大なる力を強調するが余りに、神の愛を見失ってしまった従来の歪められた神観に基づいているからである。
だから、今までのキリスト教は、愛を説くことがあっても、それ以上に、神の名において権力を振りかざし、下層の人々、異端、異教徒たちの人権を蹂躙し殺害までして来た。
それは、キリスト教がローマ帝国で迫害された最初の約400年間が過ぎて、国教として公認されてから、出て来るようになった。特に11世紀末から始まった十字軍、12世紀から始まった異端審問、15世紀から始まった中南米征服などを通してカトリックが犯した反人道的犯罪は目を覆いたくなる。
筆者は、スペインのバルトロメ・デ・ラス・カサス (Bartolomé de Las Casas) による1552年出版の『インディアス破壊についての簡潔な報告』(日本語訳、岩波文庫1976年出版)を読んで、コロンブス一行が中米にやって来て以来、如何にキリスト教の征服者たちが、現地のインディオたちを悪魔の子孫と見なすが余りに数え切れないほど彼らを殺害して、彼らの土地と財宝を奪ったかを知り、あまりにも哀れなインディオたちのことを思い号泣した。
捕縛されたあるインディオ族長が火あぶりで殺される前に、洗礼を受ければ天国に行けるので洗礼をうけるか、と宣教師から訊かれた時に、天国にはキリスト教信者がいるのかと逆に訊いた。
勿論、宣教師からの答えは、天国にはキリスト教信者がいるということであった。
その時、族長は、そんな残酷な人たちと一緒にはなりたくはなく、それよりも仲間のいる地獄の方がいい、と断言して殺されて行った。
これほど痛烈なキリスト教批判がどこにあるであろうか。
キリスト教の犯罪はカトリックのみならずプロテスタントにも見られる。
詳述は避けるが、宗教改革直後に起きたドイツ農民戦争の残忍な結末、17世紀におけるプロテスタント・スコラ主義の目も当てられない驕慢性、北米における非人道的な奴隷制度やインディアン虐待などは、プロテスタントによって起こされたものである。
このような数多くのキリスト教の犯罪の結果、差別されて虐待された人々の大きな恨みが残り、この世界は未だに分断され混乱している。
十字軍以来キリスト教を憎んで来たイスラム教は今もテロをもたらしているし、キリスト教に恨みを持つ共産主義と無神論が未だに存在するし、プロテスタント・スコラ主義に反旗を翻して出て来た啓蒙主義の世俗的伝統の脅威が今も続いているし、資本主義と手を組んだ南米カトリック上層部に恨みを持つ解放神学が21世紀になった今でもパラグアイやニカラグアなどの政権を通して脅威を振りまいているし、また北米では、奴隷制から始まった根深い黒人問題、土地を奪われて居留地に追いやられた哀れなインディアンたちの問題が未だに尾を引いている。
これこそ、神の愛よりも神の力を振りかざして来たキリスト教がもたらした社会問題でなくて何であろうか。
キリスト教を以ってしては、この深刻な社会的問題を絶対に収拾できないことを、統一教会に反対する牧師たちは知るべきである。そして、統一教会こそ、キリスト教がもたらしたこのような問題を解決できる大きなビジョンを持っていることを知るべきである。
拉致監禁を知るための書籍紹介
画像をタップしてその他の書籍紹介をご覧ください。